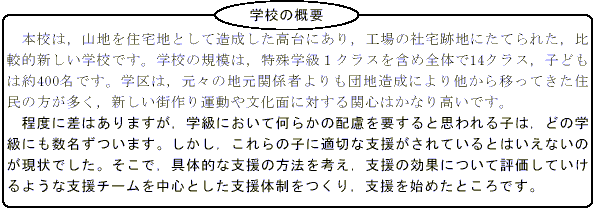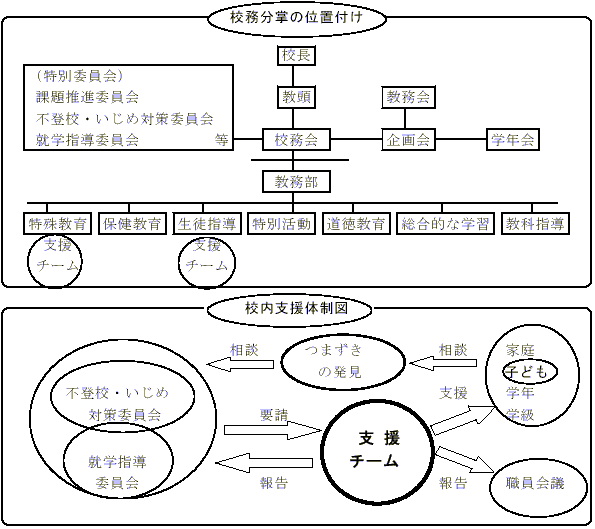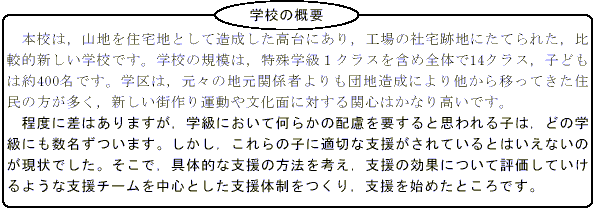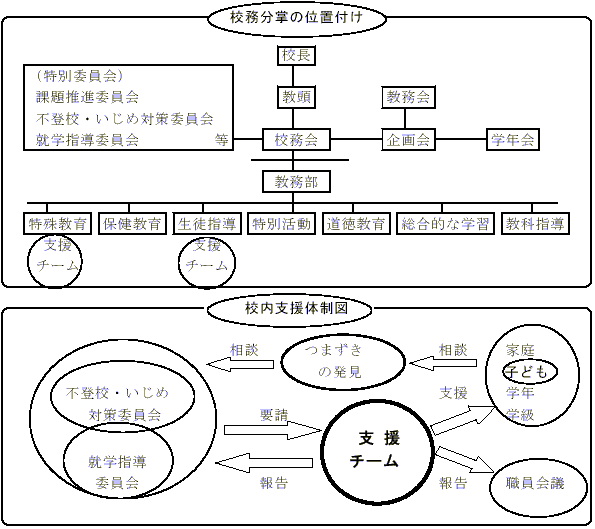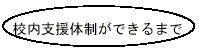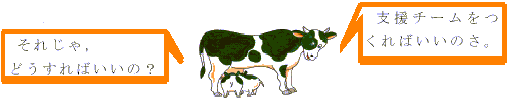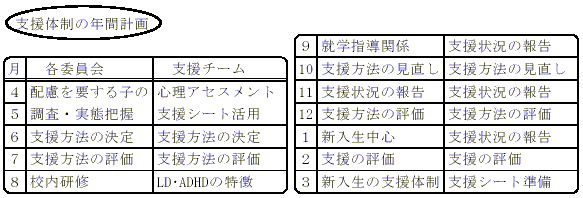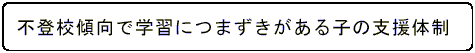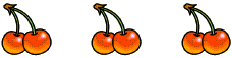| Ⅰ |
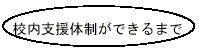 |
| |
1 |
既存の特別委員会の見直し |
| |
|
(1) |
校内就学指導委員会の見直し |
| |
|
|
① |
配慮を要する子の実態把握に,とどまっていないか? |
| |
|
|
② |
特殊教育等の取り出し指導を進めるための場になってはいないか? |
| |
|
(2) |
不登校・いじめ対策委員会の見直し |
| |
|
|
① |
事実の伝達の場に,とどまっていないか? |
| |
|
|
② |
対処的指導になっていないか? |
| |
|
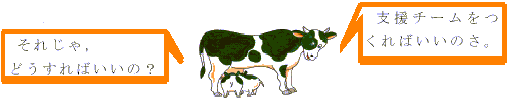 |
| |
2 |
支援チームの設立のために |
| |
|
(1) |
コーディネーターの選出(生徒指導主事) |
| |
|
|
① |
子どもや学区の様子をよく知っており,相談機関とも連携がとれている。 |
| |
|
|
② |
対処的な指導に加え,予防的な支援をしたいと考えている。 |
| |
|
(2) |
スタッフの選出 |
| |
|
|
① |
教育相談員等による心理面からの支援 |
| |
|
|
② |
特殊教育担当者や経験者による特殊教育的な立場からの支援 |
| |
|
|
③ |
養護教諭等による保健安全的立場からの支援 |
| |
|
(3) |
職員に対する理解啓発 |
| |
|
|
① |
校内研修による支援チームの必要性と役割等の共通理解 |
| |
|
|
② |
LD(学習障害)やADHD(注意欠陥/多動性障害)等についての正しい理解や支援の研修 |
|
| Ⅱ |
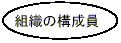 |
| |
校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・教育相談員・養護教諭・特殊教育担当者・保護者・相談機関・医療機関等 |
|
| Ⅲ |
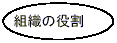 |
| |
○ |
支援シートを用いて,具体的な支援の手立て(何を,どこで,形態は,誰が,いつまで等)を考える。 |
| |
○ |
必要に応じて教育アセスメントを実施する。 |
|
Ⅳ |
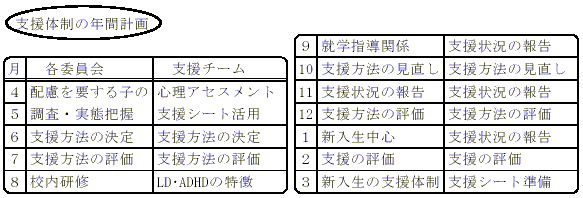 |
|
| Ⅴ |
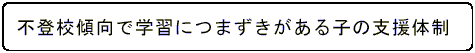 |
| |
1 |
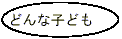 |
| |
|
○ |
中学年の子どもで,怠学傾向にあります。 |
| |
|
○ |
親の養育態度に問題があり,遅刻しようが,休もうが,「学校に行ってもどうせ勉強もできないし,つまらないだろう」と,あまり気にしません。。 |
| |
|
○ |
入学当初から,友人に対し攻撃的であり,言動が乱暴になりがちで,友人のいやがることを平気で言ったりやったりしてしまいます。 |
| |
|
○ |
学習では,課題に対する集中が持続せず,基礎・基本的なことが身に付いているとはいえません。図工や理科等には興味を示し,あとは声をかけてもほとんど参加せずに,友だちにちょっかいをだしたり,ぼんやりしていることが多いです。 |
| |
|
○ |
お手伝いなど進んで一生懸命やるようなすばらしい一面ももっています。 |
| |
2 |
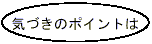 |
| |
|
○ |
就学指導関係や生徒指導関係で名前が出ることが多く,問題行動があればその都度指導しながら,注意して見守ってきました。 |
| |
|
○ |
望ましい生活習慣を身に付けさせること,対人関係に関すること,目的を持った学校生活を送らせること,学習の基礎・基本を身に付けさせることなど多くの支援すべきことがあります。 |
| |
|
○ |
そこで,よりよい支援を目指して,支援チームによる多角的な面から支援の方針や内容を話し合い,支援を進めることにしました。 |
| |
3 |
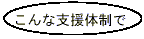
 |
| |
|
(1) |
支援の経過 |
| |
|
|
① |
支援が必要な状況の把握 |
| |
|
|
|
| ○ |
不登校(怠学)傾向であり,家庭の協力が得られません。(生徒指導面から) |
| ○ |
基本的な生活習慣が身に付いていません。(生徒指導面から) |
| ○ |
学習の決まりを守ることができず,集中の持続が難しいです。(就学指導面から) |
| ○ |
該当学年で習得すべき基本的な学力が身に付いていません。(就学指導面から) |
|
| |
|
|
② |
支援チームによる支援の方針や内容の決定 |
| |
|
|
|
| ◎ |
学校は楽しいところです。一つ一つのことに自信をもたせます。(基本方針) |
| ○ |
よりよい生活習慣を身に付けさせていきます。 |
| ○ |
場に応じた言動ができるようにさせていきます。 |
| ○ |
図工や理科を中心にがんばりを認め,学習に対する自信をもたせます。 |
| ○ |
保護者に対する協力を要請します。 |
|
| |
|
(2) |
支援の実際 |
| |
|
|
① |
登校に関して |
| |
|
|
|
| ○ |
欠席した時は連絡はするが,登校刺激はしないで本人の意志に任せました。 |
| ○ |
遅刻でも来たことを認め自然な形で学習に参加できるように配慮しました。 |
|
| |
|
|
② |
生活に関して |
| |
|
|
|
| ○ |
身辺の片付けや当番活動では,担任と一緒に行い,よりよい生活習慣を体験させ徐々に身に付けさせていきました。 |
| ○ |
本人の話をよく聞くようにして(特に,思いどおりにならないときや機嫌が悪いときは早めに),心理的な安定を心がけました。 |
|
| |
|
|
③ |
学習に関して |
| |
|
|
|
| ○ |
図工や理科の学習で教科書やノートを出さないと学習できないような場面を多くしていきました。 |
| ○ |
図工の作品や理科の観察実験では,迷っているときにさりげなく手助けをし,いかにも自分でできたと思えるように配慮しました。 |
|
| |
|
|
④ |
保護者に関して |
| |
|
|
|
| ○ |
少しずつ本人の現状と学校の考えを話し,保護者の願いを聞き,よりよい生活や学習ができるように協力を要請しました。 |
| ○ |
スナック菓子中心の生活なので,少しずつ食事中心になるよう心がけてもらい,健康面にも配慮していただけるようお願いしました。 |
|
| |
|
|
⑤ |
「ボランティア・ティーチャー」(学生さんや地域の人材を活用したお手伝い)の協力 |
| |
|
|
|
| ○ |
定期的とはいえませんが,ノートチェックや練習問題の丸付けなど授業のお手伝いをしてもらえることがあり,その際に必ず声をかけてもらうようにしました。 |
|
| |
|
(3) |
支援の結果 |
| |
|
|
① |
登校に関して |
| |
|
|
|
| ○ |
祖母や祖父の協力も得て,学校に送ってくるなど,保護者の協力が少しずつ得られるようになってきました。そのためでしょうか,まだまだ遅刻は多いですが,欠席は,週に1日から2日程度になってきました。 |
|
| |
|
|
② |
生活に関して |
| |
|
|
|
| ○ |
担任と一緒に活動する中で,徐々に家庭でのことなどを話すようになってからは,少しずつ感情が抑えられるようになってきています。 |
| ○ |
「ボランティア・ティーチャー」とのコミュニケーションも楽しみにしています。(休み時間にも時々顔を見せてくれて,話し相手になっています。) |
| ○ |
身辺の片付けや当番活動は,担任と一緒なら嫌々でもやるようになってきました。 |
|
| |
|
|
③ |
学習に関して |
| |
|
|
|
| ○ |
校内絵画展で,ヘチマを伸び伸びと描き(担任の手も入っていますが),金賞となり,自分でやったことに自信をもてるようになってきました。 |
| ○ |
その後のパソコンを使った学習などでは,やり方を自分から聞いてくるなどの積極性も出てきました。 |
| ○ |
声をかければ,図工や理科以外の教科でもノートや教科書を開くようになり,時々,気が向けば板書を写す姿も見られるようになってきました。 |
|
|
| Ⅵ |
 |
| |
1 |
支援体制づくりのポイント |
| |
|
(1) |
コーディネーターの設定 |
| |
|
|
○ |
新たな支援体制づくりには,その必要性を感じ,情報を整理し,臨機応変な支援チームを編制し,運営できる人が必要です。(コーディネーター) |
| |
|
|
○ |
本校では,学校や子どもをよく知っている生徒指導主事をコーディネーターとして,支援体制づくりが少しずつ進められています。 |
| |
|
(2) |
支援チームのスタッフ |
| |
|
|
○ |
それぞれの分野(生徒指導,特殊教育など)に精通している方も必要ですが,各分野の考えを統合できるような柔軟な考えのできる方もいたほうが,支援の方針が立てやすいです。 |
| |
|
|
○ |
ケースに応じて,支援チームのスタッフは変化があってもいいと思います。必要最小限のスタッフで,フットワークよく動けた方が実践的です。 |
| |
|
(3) |
チェックリストの活用 |
| |
|
|
○ |
配慮を要する子どものピックアップを行う際,「特に配慮を要するのか」「それほどではないが配慮した方がいいのか」「何となく気になるのか」などの情報もあった方が活用しやすいです。 |
| |
|
(4) |
支援シートの活用 |
| |
|
|
○ |
具体的な支援の方針や内容を共通理解し,全職員で該当の子を支援するという意識の高揚や協力体制づくりに有効です。 |
| |
|
|
○ |
支援シートに基づいた支援の経過や考察を生かして,修正をしながら今後に向けて支援を深めていくことができます。 |
| |
2 |
今後の課題 |
| |
|
(1) |
全職員への理解啓発 |
| |
|
|
○ |
全職員で支援をするためには,子ども理解や障害に対する一般的な研修から,個々のケースにあわせた具体的な支援の方法など,さらに研修の充実を図ることが大切です。 |
| |
|
(2) |
支援体制の充実 |
| |
|
|
○ |
支援チームの作戦会議(具体的な支援の方針・内容等)の時間の確保が難しいようなので,できるだけフットワークを軽くして開催していきたいです。 |
| |
|
|
○ |
ケースによっては,専門機関との連携により,さらに支援効果を高めていくことも必要です。 |
| |
|
|
○ |
不登校いじめ対策委員会と就学指導委員会をあわせて,支援委員会とし,支援を考えていくことができれば,校務分掌上の負担も多少軽減され,より機能的な支援体制になると考えられます。(モデル2) |
| |
|
|
○ |
ティーム・ティーチングや少人数指導をはじめ,ボランティアティーチャーなど実際に支援できる人材の確保もしていきたいです。 |
|
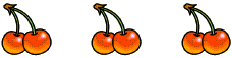 |