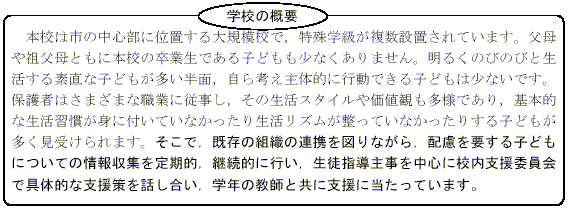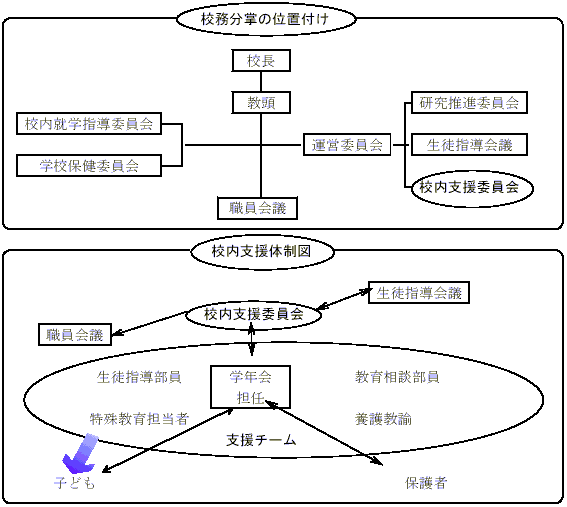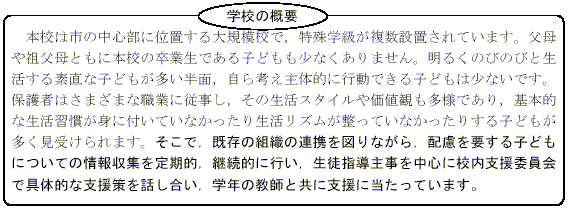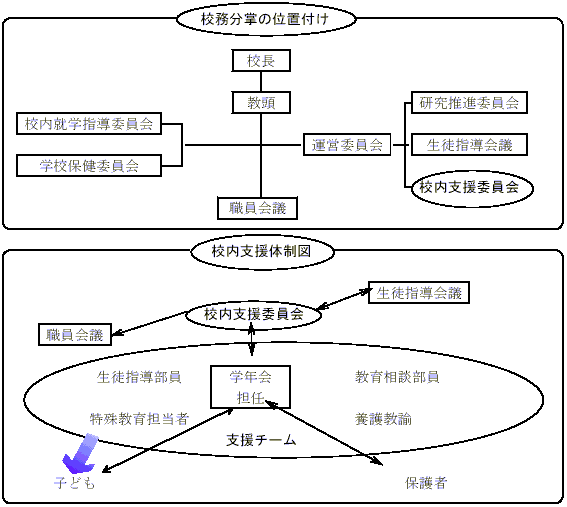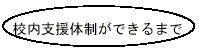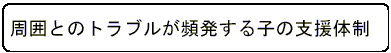| Ⅰ |
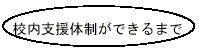 |
| |
1 |
子ども理解や支援についての教師の意識改革 |
| |
|
生徒指導上で話題になる子どもや集団不適応の子どもについては,生徒指導会議や学年会からの報告などでその実態の共通理解はされていました。しかし,ほとんどの場合その支援などは担任や学年の教師に任されていました。そこで,不登校児童以外でも学校全体で支援していこうとする意識を持てるような雰囲気づくりをする必要がありました。また,LD(学習障害)やADHD(注意欠陥/多動性障害)などについての正しい理解やよりよい支援のあり方などについては学校全体として研修を進める必要があります。 |
| |
2 |
教務主任や生徒指導主事との連携 |
| |
|
配慮を要する子どもに対する支援を考えたときの問題点を洗い出し,その改善策を特殊教育担当者から提案しながら話し合いをしました。提案は,特殊教育担当者から行いましたが,職員の意識上や支援委員会の目的からも支援委員会のコーディネーターとしては生徒指導主事が望ましいようです。
新年度になって,校務分掌上の担当が代わるときには,特に連携を図るように注意することが重要です。 |
| |
3 |
組織づくり |
| |
|
会議の数を増やさないことや,メンバーを最小限にして動きやすくすること,現在の組織を最大限に活用することなどを考慮して組織を作りました。本校では,支援委員会のメンバーは,当初,生徒指導主事・教育相談担当・特殊教育担当・養護教諭の4名で考えましたが,学年主任は必ず参加したいという要望と校長や教頭も可能な限り出席したほうがよいという意見を取り入れました。また,支援チームは学年会をベースとして機能させることにしました。対象となる子どもの状態によっては,生徒指導担当・教育相談担当・特殊教育担当・養護教諭などが支援チームのメンバーとなることもあります。 |
|
| Ⅱ |
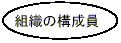 |
| |
| 校内支援委員会 |
: |
(校長・教頭)
生徒指導主事,教育相談主任,特殊教育主任,養護教諭
当該学年主任,担任 |
| 支援チーム |
: |
当該学年会のメンバー
ケースによって,生徒指導担当者,教育相談担当者,特殊教育担当者や養護教諭が加わります。 |
|
|
| Ⅲ |
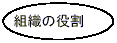 |
| |
| 校内支援委員会 |
: |
配慮を要する子どもを共通理解するための会議や研修の企画
配慮を要する子どもの実態把握
配慮を要する子どもへの対応の検討と支援方法(役割分担・場・形態など)の決定
支援についての連絡調整 |
| 支援チーム |
: |
具体的な支援計画の決定
対象児童への直接支援
支援方法についての評価と支援委員会への報告 |
|
|
| Ⅳ |
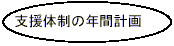 |
| |
| 月 |
ど ん な 内 容 を |
備 考 |
| 毎 月 |
子どもの実態把握 |
学年会 |
| 臨 時 |
支援方法の決定 |
校内支援委員会 |
| 4 月 |
配慮を要する子どもの共通理解 |
全職員 |
| 6 月 |
就学指導に係わる情報収集 |
学年会 |
| 7 月 |
支援方法の評価と支援委員会への報告 |
支援チーム |
| 7 月 |
配慮を要する子どもの様子や支援状況の報告 |
全職員 |
| 8 月 |
子ども理解についての校内研修 |
全職員 |
| 10月 |
就学指導対象児童の実態調査と支援方法の決定 |
支援チーム
校内就学指導委員会 |
| 12月 |
支援方法の評価と支援委員会への報告 |
支援チーム |
| 12月 |
配慮を要する子どもの様子や支援状況の報告 |
全職員 |
| 1 月 |
就学指導の経過報告 |
校内就学指導委員会 |
| 2 月 |
支援方法の評価と支援委員会への報告 |
支援チーム |
| 3 月 |
支援体制の反省と次年度にむけてのまとめ |
校内支援委員会 |
|
|
| Ⅴ |
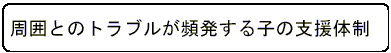 |
| |
1 |
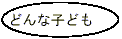 |
| |
|
○ |
落ち着きがない(体育は大好き) |
| |
|
○ |
先生や友達の話を聞いていない(何でも自分勝手にやりたがる) |
| |
|
○ |
興味のある物事やその方向に衝動的に動いていく(いつでも,どこでも) |
| |
|
○ |
ことばより先に行動(でも,おしゃべりは大好き) |
| |
2 |
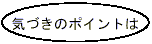 |
| |
|
○ |
給食の準備時間自分が給食当番なのに金魚や亀の水槽の前にずっと動かずにいた。 |
| |
|
○ |
休み時間,砂場で遊んでいるところにボールが転がってきた。そのボールを追いかけてきた他学年の子どもにいきなり砂を投げつけた。 |
| |
|
○ |
授業中,気になることがあると急に話し出したり質問し続けたりする。 |
| |
|
○ |
集会の時間,前の子の髪の毛を触り「やめて」と言われてもやめようとしない。少し長い時間になると寝そべってしまう。 |
| |
3 |
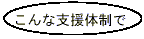 |
| |
|
(1) |
支援の経過 |
| |
|
|
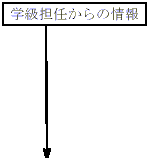 |
|
入学当初から行動が目立ち,配慮を要する子どもとして話題にあがっていました。
周囲とのトラブルが頻発して苦情が担任まで届くようになり,教室内では目が離せなくなってきた状況が,担任から生徒指導主事や特殊教育担当者に伝わりました。 |
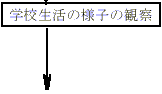 |
|
学年内の教師や生徒指導主事,特殊教育担当者(情緒障害特殊学級担当)が情報を収集し,整理しました。 |
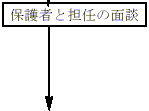 |
|
学校生活の様子を保護者に伝えました。入学前の集団生活の場での本児の様子に関しては,「個性である」といい続けてきた保護者であるという情報を得ていたので,担任だけで事実のみを伝えることにしました。 |
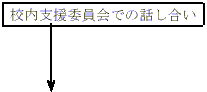 |
|
様々な情報を整理して支援方針を決定し,支援チームによる支援をスタートさせるとともに担任からその支援方針を保護者に伝えることなどを話し合いました。 |
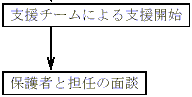 |
|
特殊教育担当者も同席して,心理アセスメントの結果などを参考にしながら今後の支援について話し合いました。 |
|
| |
|
(2) |
支援の実際 |
| |
|
|
① |
学年のスタッフによる直接的支援 |
| |
|
|
|
日常の学校生活場面では,学年のスタッフが心配りをし,声をかけるなど,担任とともに直接的支援を行いました。生活科や体育などではTTを意図的に組むようにしました。 |
| |
|
|
② |
特殊教育担当者(情緒障害特殊学級担当)による支援 |
| |
|
|
|
ア |
教室を頻繁に訪問したり,活動の様子を観察したりしながら子どもとかかわりを持ち,実態を把握するとともに心理アセスメントを行うための関係づくりをしました。その後,客観的な資料とするための各種の診断テストを行いました。 |
| |
|
|
|
イ |
担任や保護者に子どもの状態をどうとらえるかやその特性に応じた望ましい対応のしかたがあることなどを伝えていきました。ADHDやLDも疑われたので,スクリーニングテストや社会生活能力検査なども紹介して行いました。検査後は,両親との話し合いの場を設け,心理アセスメントの結果を伝え,情緒教室での指導を受けることを勧めたり専門機関の受診などについても話し合いました。
担任にはADHDやLDに関する情報を伝え,教室での対応のしかたで状態が変わっていくことがあることを伝えるようにしました。 |
| |
|
|
|
ウ |
情緒教室で,個別指導と小集団指導を始めました。 |
| |
|
(3) |
支援の結果 |
| |
|
|
・ |
自己コントロールしようとする意識のあらわれ(「朝から,いじわるしてないよ。」) |
| |
|
|
・ |
父母の意識の変化(個性だけではないんだ。何とかしなくちゃ。) |
| |
|
|
・ |
専門機関の受診(一つ一つていねいに教えていきましょう。)(もっともっとお母さんがこの子とかかわって) |
| |
|
|
父母の意識と子どもへのかかわり方が大きく変化したことで,子ども自身の気持ちや行動にも変化がみられるようになりました。まだうまくコントロールすることはできませんが,自分の行動を冷静に振り返ることができるときもあります。また,担任や父母が,子どもの社会性の未発達や発達のかたよりなどが粗暴で落ち着きのない行動につながっていることにも気付くことができました。 |
|
| Ⅵ |
 |
| |
1 |
支援体制づくりのポイント |
| |
|
・ |
校内支援委員会の立ち上げまでには,特殊教育担当と生徒指導主事と教務主任の連携が不可欠です。 |
| |
|
・ |
校内支援委員会のコーディネーターは生徒指導主事が適任です。 |
| |
|
・ |
学校内の実情に合わせた既存の組織の活用や再編などの工夫をして,活動しやすくて継続できる体制にすることが大切です。 |
| |
|
・ |
何よりもまず,配慮を要する子どもについて学校全体で支援していこうとする意識を高めることが大切です。 |
| |
2 |
今後の課題 |
| |
|
組織として立ち上げて1年目の本年度は,職員の意識の中で校内支援委員会の存在ははっきりしなかったようでした。しかし,1学期の支援状況の報告や実際の支援の様子などから少しずつ理解できてきたように思われます。校内支援委員会の目的から見ても,組織として立ち上げた後の活動状況が問題になります。定期的な開催が望ましいと思いつつ,現実的には随時開催のうえ構成員全員が揃って話し合えることはほとんどありませんでした。必要に応じた開催と学校全体の会議などとともに時間を確保した開催をしていけるようにしていきたいです。
子どもの実態を把握しやすい学年のスタッフを支援チームの母体としたことは,有効であったように思われます。さらに適切な支援をするために,子ども理解や問題行動などについての研修を学校全体として続けていく必要があります。そのためには,特殊教育担当者も情報提供をしたり研修の推進役となれるよう努力していくことが必要です。 |
|
| |
参考資料 |
| |
「校内支援委員会報告」(用紙) |
| |
「個別の支援計画」(支援シート) |