| ア |
指導者の学習追究プロセス明確化と生徒への活動マニュアル「エコービクス」の提示 |
| |
追究プロセスを明確にしたことは,指導者にとっても生徒にとっても活動全体の見通しをもつことができ,活動の焦点化を図ることができた。第1段階では,合唱への取り組みや歌唱活動の基礎を育てることができた。第2段階では,全体をとらえた課題想起が見られた。第3段階では,構成力,識別力,表現力,聴取力,関係把握力などを働かせながら,より豊かで美しい合唱になるよう主体的な追究活動が見られた。第4段階では,表現力,聴取力,理解力などを働かせながら相互評価や自己評価を行うことができ,より高い目標がもてるようになった。生徒は活動マニュアル「エコービクス」により,合唱活動の流れや内容を把握することができ,また,課題追究に主体的に取り組むことができた。 |
| イ |
多様な学習形態
| (ア) |
個人練習・ペア練習〈授業導入時,パート練習時〉 |
| |
 導入時に「エコービクス」を活用し,個人やペアで姿勢,発声の練習を行った。個人練習では,吸気の練習(腹に手をあて,上体を前に倒して息を吸う),呼気の練習(腹に手をあて,歯擦音で少しずつなめらかに息を出す)顔の前に薄い紙を持ち,紙に息を当てて均一な息個人の呼吸練習の様子の出し方を確かめる)を行った。ペア練習では,発声練習(互いに口径や腹筋,響きを意識した声の出し方を確かめ合う)を行った。これらの練習は「豊かな響きをもった声」をつくるのに有効であった。
導入時に「エコービクス」を活用し,個人やペアで姿勢,発声の練習を行った。個人練習では,吸気の練習(腹に手をあて,上体を前に倒して息を吸う),呼気の練習(腹に手をあて,歯擦音で少しずつなめらかに息を出す)顔の前に薄い紙を持ち,紙に息を当てて均一な息個人の呼吸練習の様子の出し方を確かめる)を行った。ペア練習では,発声練習(互いに口径や腹筋,響きを意識した声の出し方を確かめ合う)を行った。これらの練習は「豊かな響きをもった声」をつくるのに有効であった。 |
| (イ) |
グループ練習〈授業導入時,パート練習時〉 |
| |
導入時にグループでカデンツ練習(Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ→Ⅰ)を行い,互いに聴き合いながら音程やバランスを調整し,美しい和声の響きを感じ取ることができた。その際,フェイストレーニングで共鳴腔を開き,さらに遠くへ声をとばすことを意識させた。パート練習では,同じパート内でグループ分けをするなど,互いに聴き合える場を設定することによって「正確な音程」を意識し,確認することができた。 |
| (ウ) |
全体練習〈パート練習時,合唱練習時〉 |
| |
パートごとの発表や半分ずつの人数での合唱を聴き合い,互いのよさや問題点を話し合うことで,より客観的な観点で自分たちの合唱追究をすることができた。それらの活動から,美しい響きやバランス,和声感が育ち,主体的に和声の豊かさや美しさを感じ取ることができるようになってきた。 |
|
| ウ |
範唱鑑賞や録音による表現と鑑賞の関連 |
| |
課題を見つけ表現の工夫をするために,パート別範唱CD鑑賞や他の生徒の合唱鑑賞を行った。生徒が必要なときに,パート別の範唱を聴くことができる再生装置を用意したコーナーを設置したことは,自分たちの声と範唱を比較することができ,主体的に課題解決する一助となった。また,小グループで活動させるときにも,このコーナーは効果的であった。合唱を録音することは,全体の響きの調和や個々の声質の調和を客観的に感じ取らせることができ,歌唱表現を工夫させるのに有効であった。その際,和声や音楽の諸要素に着目して鑑賞でき,それらを基に話し合いながら表現の工夫を積み重ねることができた。これらは,相互評価を基にした自己評価につながり美しさを感じさせる手だてとなった。 |
| エ |
授業導入時における発声練習の工夫 |
| |
生徒は活動マニュアル「エコービクス」により,活動開始と同時に,呼気,吸気,発声などの練習を始め,一人一人が豊かな響きをつくるための活動を主体的に行った。これは基本的な技能を身に付けるためにも効果があり,個人やペアでの基礎トレーニングやカデンツ練習で互いの声を聴き合い,和声の響きの美しさを感じ取れるようになっていった。 |
| オ |
評価の具体的な達成規準の具現化 |
| |
評価の観点とその達成規準について下表のように具体化することで,活動を段階的に評価することができ,一人一人の支援に生かすことができた。
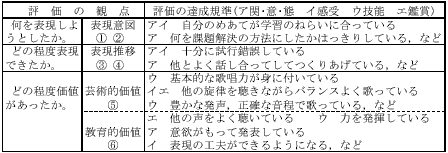 |
| |
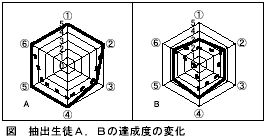 抽出生徒2名の表現に関する達成度を検討してみた。Aは音楽が好きで努力する生徒,Bは音楽に興味が低い生徒である。観点は,①めあてがもてたか,②具体的な追究課題がもてたか,③表現を工夫しようとしたか,④友達と話し合ったか,⑤美しい発声,正しい音程か,⑥発表はよくできたか,の6つである。図はそれをレーダーチャートに表したものである。第2時(点線)に比べ,第6時(実線)の方が達成度が高くなった。その他の生徒についても,達成度を調べてみるとほぼ同様の向上が見られた。
抽出生徒2名の表現に関する達成度を検討してみた。Aは音楽が好きで努力する生徒,Bは音楽に興味が低い生徒である。観点は,①めあてがもてたか,②具体的な追究課題がもてたか,③表現を工夫しようとしたか,④友達と話し合ったか,⑤美しい発声,正しい音程か,⑥発表はよくできたか,の6つである。図はそれをレーダーチャートに表したものである。第2時(点線)に比べ,第6時(実線)の方が達成度が高くなった。その他の生徒についても,達成度を調べてみるとほぼ同様の向上が見られた。 |
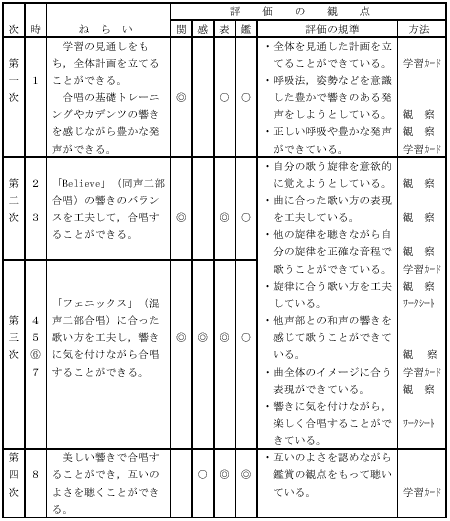
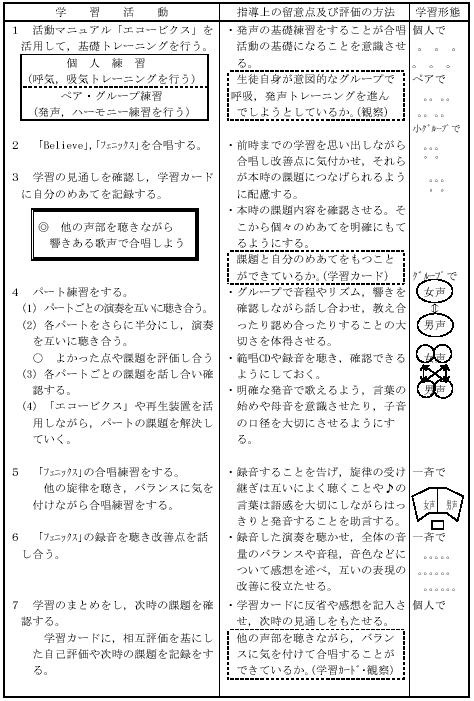
 導入時に「エコービクス」を活用し,個人やペアで姿勢,発声の練習を行った。個人練習では,吸気の練習(腹に手をあて,上体を前に倒して息を吸う),呼気の練習(腹に手をあて,歯擦音で少しずつなめらかに息を出す)顔の前に薄い紙を持ち,紙に息を当てて均一な息個人の呼吸練習の様子の出し方を確かめる)を行った。ペア練習では,発声練習(互いに口径や腹筋,響きを意識した声の出し方を確かめ合う)を行った。これらの練習は「豊かな響きをもった声」をつくるのに有効であった。
導入時に「エコービクス」を活用し,個人やペアで姿勢,発声の練習を行った。個人練習では,吸気の練習(腹に手をあて,上体を前に倒して息を吸う),呼気の練習(腹に手をあて,歯擦音で少しずつなめらかに息を出す)顔の前に薄い紙を持ち,紙に息を当てて均一な息個人の呼吸練習の様子の出し方を確かめる)を行った。ペア練習では,発声練習(互いに口径や腹筋,響きを意識した声の出し方を確かめ合う)を行った。これらの練習は「豊かな響きをもった声」をつくるのに有効であった。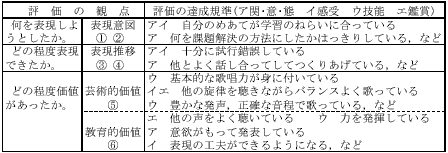
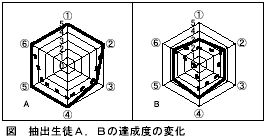 抽出生徒2名の表現に関する達成度を検討してみた。Aは音楽が好きで努力する生徒,Bは音楽に興味が低い生徒である。観点は,①めあてがもてたか,②具体的な追究課題がもてたか,③表現を工夫しようとしたか,④友達と話し合ったか,⑤美しい発声,正しい音程か,⑥発表はよくできたか,の6つである。図はそれをレーダーチャートに表したものである。第2時(点線)に比べ,第6時(実線)の方が達成度が高くなった。その他の生徒についても,達成度を調べてみるとほぼ同様の向上が見られた。
抽出生徒2名の表現に関する達成度を検討してみた。Aは音楽が好きで努力する生徒,Bは音楽に興味が低い生徒である。観点は,①めあてがもてたか,②具体的な追究課題がもてたか,③表現を工夫しようとしたか,④友達と話し合ったか,⑤美しい発声,正しい音程か,⑥発表はよくできたか,の6つである。図はそれをレーダーチャートに表したものである。第2時(点線)に比べ,第6時(実線)の方が達成度が高くなった。その他の生徒についても,達成度を調べてみるとほぼ同様の向上が見られた。