5.授業研究 |
| 研究主題に関する基本的な考えと実態調査の結果を踏まえ,一人一人のよさを生かしながら,主体的な活動を通し音楽の豊かさや美しさを感じ取らせる手だてを講じ,2年間にわたり小学校,中学校各2校で授業研究を行った。2年目にあたる本年度の小学校,中学校各1校における授業研究は以下の通りである。 |
| |
| 【授業研究1】 |
| |
小学校第4学年
「いい音えらんで」における,音や音楽のイメージを感じ取り自分らしい表現力を育てる指導の工夫 |
| |
(1) |
授業研究のねらい |
| |
本研究では,音楽分科会の研究主題を次のようにとらえて研究していくことにした。
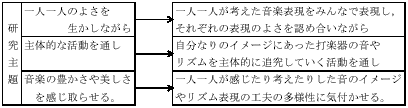
これらの活動を通して,音楽には様々な表現があることに気付かせ,児童一人一人に自分のイメージをもって音楽表現しようとする態度を身に付けさせることをねらいとした。
実態調査の結果を見ると,子どもたちは旋律やリズム,強弱や速さなどの音楽の諸要素の一つ一つに注目して音楽を表現しようとしていると考えられる。それに対して,教師は歌詞の内容や楽曲の響き,曲想,雰囲気などの音楽全体のイメージをとらえて音楽活動をさせたいと考えていることが分かる。ここでは両者の意識にずれがあるように感じられるが,児童に「楽譜に記されていることを表面的にとらえるだけではなく,自分が感じ取った音楽のイメージを表現するために,旋律の歌い方やリズム,強弱,速さなどを工夫するんだ」と意識させることができれば,教師の願いと児童の活動は一致してくるものと考えた。
そこで,本研究では打楽器を使って児童に音のイメージをもたせることに重点を置き,音から受けるイメージと自分の表現したいイメージが一致するような音を探す活動を通して,自分らしく表現するという意識をもたせていくことにした。そして,表現のおもしろさに気付かせ,音楽を自分のものとして表現する喜びや,音楽表現の豊かさや美しさを感じ取らせる活動に発展させていく学習指導の在り方を追究していくことにした。 |
| (2) |
イメージを感じ取り,自分らしい表現力を育てるための手だて
| ア |
表現と鑑賞の関連 |
| |
子どもたちにとってラテンパーカッションはあまりよく知られていない楽器であると思われる。そこで,楽器の持ち方や奏法などをビデオやレーザーディスクを活用して鑑賞することで,どのように演奏したらよいかイメージをもつことができ,自分の表現に生かすことができるようにする。
また,教師の演奏で様々な奏法の工夫を聴き取らせることも,音に対するイメージを育て,自分の楽器の表現を工夫するきっかけになると考える。友だちの演奏を鑑賞することも,自分のイメージとの違いに気付き,様々な音楽表現があることや,自分らしい表現を認識することにつながり,自分らしい表現を工夫するきっかけになるようにする。 |
| イ |
指導法の工夫
| (ア) |
「リズムパターン・カード」の活用 |
| |
音楽の授業の導入ではよく既習曲を歌うことがあるが,歌に手拍子を入れてリズムを感じながら歌う活動を取り入れていく。事前に1小節程度の様々なリズムを表した「リズムパターン・カード」を用意し,カードに示されたリズムを手で打ちながら歌っていく活動をする。ここで身に付けた技能が,後のリズム伴奏をする場面で生かされてくるものと考えられる。
また,打楽器によるリズム伴奏をつくる場面では,「リズムパターン・カード」の中からリズムを選ばせる。教科書には3つの楽器についてはリズム伴奏の例が載っているが,他の楽器については何も書かれていない。そこで,事前にそれぞれの楽器に合うようなリズムをつくっておき,児童に選ばせるようにし,自分でリズムを創作できる児童には,「リズムパターン・カード」にとらわれずに自分でつくるように指導する。 |
| (イ) |
音楽学習ゲームやクイズで音のイメージづくり |
| |
この題材では,各打楽器の音色のイメージをもたせるために,音楽学習ゲームやクイズを通して,次のようなステップでイメージづくりをしていく。
まず,「音当てクイズ」で各打楽器の音色のイメージをつかみ,音を聴き分けられるようにしていく。方法は単純で,児童に見えないようにして各打楽器の音を出し,どの楽器の音かを楽器を指さしたり楽器の名前を言わせたりして当てさせる。この活動で,どの楽器がどんな音を出すのかというイメージをもたせ,後の活動につなげる。
次に,楽器の音を言葉や物にたとえて表現する「音の連想ゲーム」を行っていく。まず,各打楽器の音を出し,そのイメージを「明るい音」とか「頭をたたかれたような音」,「キツツキが木をつついているような音」のように言葉で表現させる。また,マレットや奏法を変えて音を出し,同じ楽器でも様々な音が出ることにも気付かせるようにする。
そして,「イメージ音さがしゲーム」を行う。音の連想ゲームとは反対に,物や動作・様子などを表す言葉から,そのイメージに合う楽器や奏法を考えていく。稲光→シンバル,背中がかゆい→ギロ,地震→バスドラムのロールなどのように,言葉のイメージから音のイメージへと結びつけていく。 |
|
| ウ |
児童一人一人のよさを認める相互評価 |
| |
クイズやゲームで自分のイメージを発表する場面では,共感的に発表を聴いて,よかったところを「アドバイス・カード」に記録し,相手に伝えるようにする。演奏後の拍手によっても友だちのアイデアや努力をたたえるように指導する。よかったところや「こうした方がもっとよいと思う」というアドバイスは言ってもよいが,否定的なことは言わないルールにする。この態度は,他の教科の発表の場面でも指導して定着させておく。認められれば誰でもうれしいので,もっとアイデアを出そう,自分もよい発表をしようとする意欲につながるようにする。 |
| エ |
試行錯誤ができる時間の確保 |
| |
児童が楽器を選ぶ場面では,様々な楽器の音を自分で確かめながら,イメージに合った楽器を選ぶまでに時間がかかると思われる。また,練習をする場面でも,選んだ楽器で自分が自由に表現ができるかどうか悩んだり,楽器のイメージに合うリズムがなかなか見つからなかったりするなど,時間がかかるものと思われる。このような活動がある場合,1時間では児童の活動が盛り上がったところで終わってしまうことが予想される。そこで,2時間連続の授業を設定したり活動内容を精選したりすることで,児童が試行錯誤しながら練習できる時間を確保していく。 |
|
| (3) |
授業の実践
| ア |
題材 いい音えらんで |
| イ |
学習の流れと評価(9時間扱い 本時は第三次の第二時)
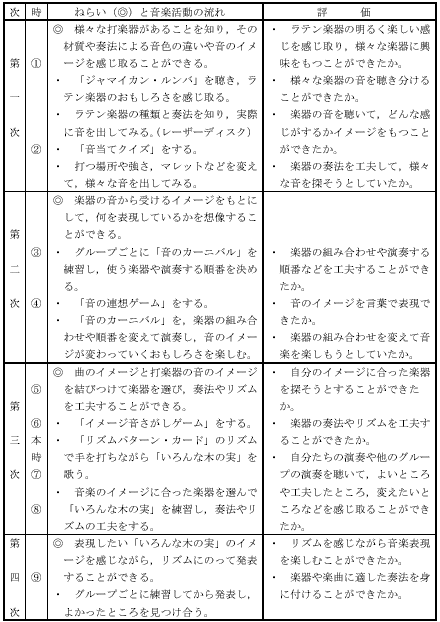 |
| ウ |
本時の学習 |
| |
(ア) 目標 |
| |
楽曲や歌詞から得たイメージに合った音を探そうとすることができる。 |
| |
(イ) 展開
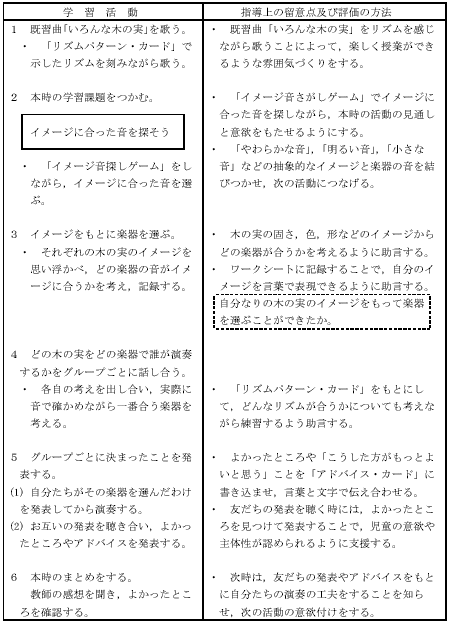 |
|
| (4) |
授業の結果と考察
| ア |
「リズムパターン・カード」の活用 |
| |
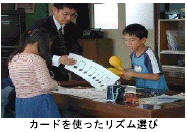 リズム伴奏を考える場面では,「リズムパターン・カード」をよりどころとして,自分の楽器のリズムを選び,練習することができた。導入時にリズム打ちの練習を兼ねて「リズムパターン・カード」を使った既習曲の歌唱をしている効果で,リズムの楽譜をあまり苦労せずに読みとることがカードを使ったリズム選びできた。
リズム伴奏を考える場面では,「リズムパターン・カード」をよりどころとして,自分の楽器のリズムを選び,練習することができた。導入時にリズム打ちの練習を兼ねて「リズムパターン・カード」を使った既習曲の歌唱をしている効果で,リズムの楽譜をあまり苦労せずに読みとることがカードを使ったリズム選びできた。 |
| イ |
音楽学習ゲームやクイズで音のイメージづくり |
| |
「イメージ音さがしゲーム」では,イメージに合った音を探そうと,児童が様々な楽器を鳴らして確かめながら音を探すことができた。ここでは,前時の「音の連想ゲーム」での経験から,言葉のイメージから思い浮かんだ楽器の音を実際に出して確かめる様子が見られた。しかし,一つの楽器に「明るい音」,「暗い音」のように相反するイメージが出てきたりして,児童のイメージは個人によってずいぶん違っており,様々なイメージに感じ取られていることが分かった。 |
| ウ |
児童一人一人のよさを認める相互評価(表現と鑑賞の関連) |
| |
他の教科の学習を通して,友だちの発表のよいところを探す習慣が身に付いてきていることもあり,友だちの発表のよいところに気が付くことができた。特に,リズムを工夫して演奏している児童のよさには全員が気が付くことができた。リズムの工夫ばかりでなく,演奏している態度や表情,全員のリズムが合っていることや音楽の感じに合っていたことなど,幅広い視野で友だちの演奏を鑑賞することができた。また,友だちの発表を聴いて自分のリズム伴奏によいところを取り込んだり,友だちのアドバイスを受け入れて自分の演奏に生かすことができたことも,鑑賞と表現の関連が図られたものと考えられる。 |
|
| (5) |
授業研究の成果と課題
| ア |
「リズムパターン・カード」の効果 |
| |
「リズムパターン・カード」は,継続的に活用することにより,楽譜からリズムを読みとる力を高めたり,リズム伴奏づくりをしやすくするのに有効であることが分かった。歌に合わせて「リズムパターン・カード」のリズムを刻むことは,パターンによっては難しかったので,今後も継続して指導していく必要性を感じた。 |
| イ |
音のイメージとリズムのイメージ |
| |
音楽学習ゲームやクイズを取り入れた指導法を工夫することにより,児童は様々な音やリズムのイメージを感じ取ることができた。音でイメージを表現する活動では,音とリズムの組み合わせでイメージを表現させるような指導法の工夫が課題として残った。 |
| ウ |
相互評価と鑑賞・表現の関連 |
| |
表現活動の前に興味・関心をもてるような鑑賞を取り入れたり,友だちの演奏のよさを見つける相互評価をすることで,活動の意欲が高まり,主体的な活動を引き出すことにつながった。また,友だちの演奏やアドバイスを自分の演奏に生かすことができ,表現を工夫するために効果があった。 |
|
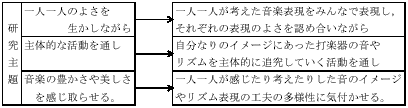
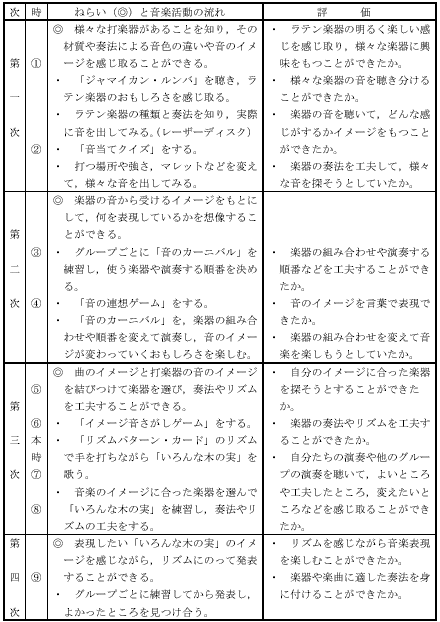
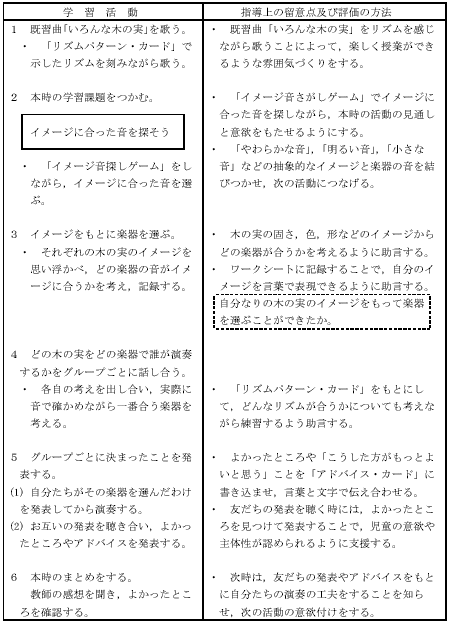
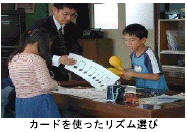 リズム伴奏を考える場面では,「リズムパターン・カード」をよりどころとして,自分の楽器のリズムを選び,練習することができた。導入時にリズム打ちの練習を兼ねて「リズムパターン・カード」を使った既習曲の歌唱をしている効果で,リズムの楽譜をあまり苦労せずに読みとることがカードを使ったリズム選びできた。
リズム伴奏を考える場面では,「リズムパターン・カード」をよりどころとして,自分の楽器のリズムを選び,練習することができた。導入時にリズム打ちの練習を兼ねて「リズムパターン・カード」を使った既習曲の歌唱をしている効果で,リズムの楽譜をあまり苦労せずに読みとることがカードを使ったリズム選びできた。