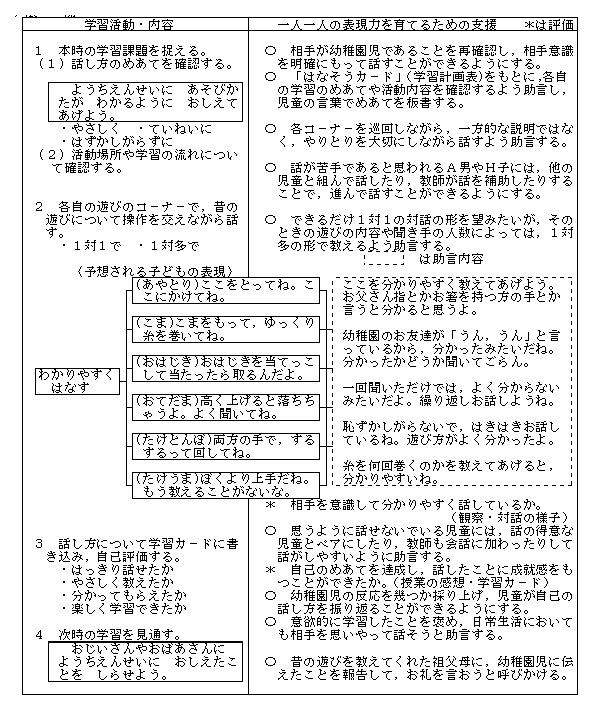
| 【授業研究1】 | |||||
| 小学校第1学年 「おはなしするのは,たのしいね」 | |||||
| (1) | 授業の構想 | ||||
|
これからの国語科学習においては,音声言語による表現活動の一層の充実を図ることが重要視されている。特に,話すこと,聞くことの双方向を踏まえた言語活動を通して,伝え合う力を育てることが求められている。 小学校低学年における音声言語による表現活動では,臆することなく自分の思いを話そうとすることが望ましく,話すことが楽しいと実感できる学習が重要である。特に,相手に伝わった喜びや満足感が得られるような学習活動を展開していく必要がある。また,話すことや聞くことの活動は,日常生活と深くかかわり合っているため,授業の言語活動も,生活に密着したものになるよう工夫することが大切である。 このような言語活動を展開するに当たっては,人とのかかわりに重点がおかれている生活科の学習との関連を図ることが効果的であると考える。また,児童の日常生活に深く結び付いている題材を生かすことで,日常生活に密着した活動が展開されるものと考えられる。 さらに,児童一人一人の音声言語の力を高めるためには,学習形態を工夫することが考えられる。児童対教師あるいは児童対児童など,個に応じて段階的に進めることが大切である。 このようなことを踏まえて,ここでは,生活科の単元 「むかしのあそびをしよう」 と関連させた 「おはなしするのは,たのしいね」 という音声言語学習の単元を構想した。人とのかかわりを十分に意識しながら話したり聞いたりすることで,相手を思いやりながら表現する態度が培われるものと考える。そのことが,児童一人一人の豊かな表現力を育てることにつながるものと考えている。 |
|||||
| (2) | 指導の手だて | ||||
| ア |
相手意識をもたせるために 1年生より昔の遊びを知らない幼稚園児を言語活動の対象にした。隣接する幼稚園の園児であるため,普段顔を合わせることが多く,抵抗なく話すことができると考える。また,日常生活において話し相手である祖父母にかかわわってもらうことで,打ち解けて話すことができるようにする。 |
||||
| イ |
目的意識をもたせるために 祖父母から教えてもらった 「昔の遊び」 を,幼稚園児に教えるという学習活動を設定していく。そのような活動を通して,教えたい内容を具体的にとらえることができるようにするとともに,一人一人が明確な目的意識をもって言語活動に取り組むことができるようにする。 |
||||
| ウ |
場面意識をもたせるために 体育館で,実際に昔の遊び道具を使って遊びながら言語活動を展開する。このことにより,操作しながら話すこと,幼稚園児を思いやりながら話すこと,1対1で話すことなどその場に応じた話し方を工夫しようとする意識を高めることができると考える。 |
||||
| エ |
評価意識をもたせるために 話したことを録音して聞いたり,相互に話を聞き合ったりして,評価意識を高めたい。また,伝わった喜びや満足感を発表し合ったり,自己評価カ-ドを活用したりすることで学習の成果を振り返ることができるようにする。 |
||||
| (3) | 学習指導案 | ||||
| ア | 単 元 おはなしするのは,たのしいね | ||||
| イ | 目 標 | ||||
| (ア) | 自分が経験したことなどについて,進んで話をしたり聞いたりしようとする。 | (関心・意欲・態度) | |||
| (イ) | 伝えたいことをはっきりさせて話したり,尋ねられた事に応答したりすることができる。 | (表現) | |||
| (ウ) | 大事なことを落とさないように気を付けて相手の話を聞くことができる。 | (理解) | |||
| (エ) | 姿勢や口形に気を付けて,はっきりした発音で話すことができる。 | (言語事項) | |||
| ウ | 表現についての意識と単元のねらい | ||||
|
|||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
|
|
|
|||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
|
|||||||||
| ↓ | |||||||||
|
|||||||||
| 次 | 時 | 主な学習活動・内容 | 形 態 | 学 習 の ね ら い |
| 生活 | むかしのあそびどうぐをつかってあそぼう。(2時間) | |||
| 1 | ① | 祖父母と昔の遊びをする会の案内を録音して,ボイスレタ-(声のお手紙)をつくる | 祖父母を意識して 1対祖父母 多対祖父母 |
|
| 生活 | おじいさんおばあさんとあそぶ会をしよう。(2時間) | |||
| 2 | ① ② |
幼稚園児を招待して遊ぶ計画を立て,遊びを紹介するための話し方を考える。 | 1対1 1対多 |
|
| ③ 本 時 |
幼稚園児との交流会において,遊び方が相手に伝わるように話す。 | 1対幼稚園児 多対幼稚園児 |
|
|
| 3 | ① | 昔の遊びを教えてくれた祖父母にお礼のビデオレタ-をつくる。 | 1対祖父母 多対祖父母 |
|
| ② | 祖父母からの手紙を読んだり,幼稚園児の声を聞いたりして話す学習を振り返る。 |
|
||
| オ |
単元でねらいたい活動意識
|
|||
| カ | 本時の学習 | |||
| (ア) |
目 標
|
|||
| (イ) | 展 開 | |||
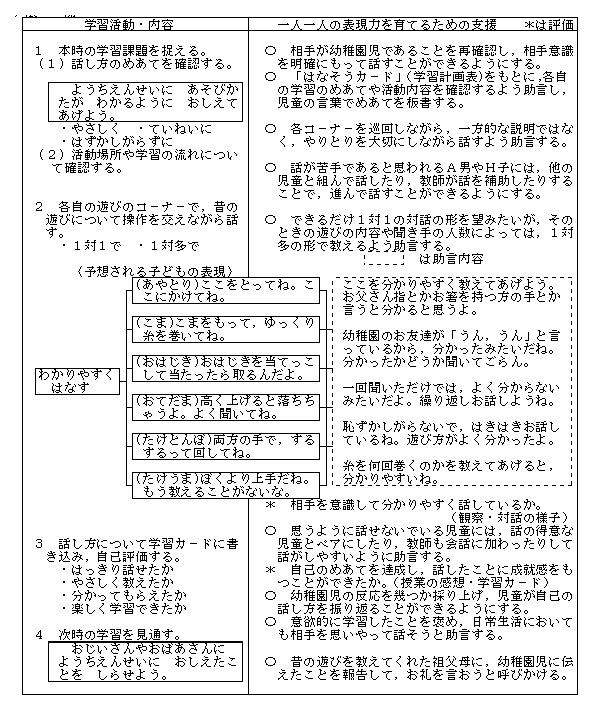
| (4) | 授業の考察 | ||||||||||||||||||
| ア |
第2次第①・②時に関する考察 教師が 「おじいさん,おばあさんから教えてもらった遊びを幼稚園のお友達にも伝えよう。」と呼びかけると,児童は 「小さい子の面倒をみるのは大変だよね。」 「泣かれたら,どうしよう。」 などと反応した。本学級の児童は,弟や妹など年下の子と遊ぶ経験が多く,幼稚園児の実態を想像することができていた。次に,どのように教えるかという方法について質問すると,児童からは,遊び方を書いて提示し,それを示しながら説明するという案が出された。そこで,教師から相手が幼稚園児であることを再度考えるよう促すと,幼稚園児は文字が読めない子もいることに気付き,話して教える以外にないという声が上が った。この段階で,児童は話すことの必要性を感じたものと考えられる。 次に,話すことについての具体的な学習目標について話し合う場を設定した。児童は, 「よくわかるようにはなす」 という 「みんなのめあて」 を決定した。 「はっきりはなす」という視点が出されなかったため,教師側から 「何を言っているのか,よく分かるように話そうね。」 と付け加えた。 さらに,一人一人が主体的に学習に取り組めるよう,個人のめあてを学習カ-ドに記入する場を設定した。資料1は,そのときの児童の反応である。これを見ると,児童が,幼稚園児を思いやりながら伝えることを強く意識していることが分かる。このような目標を基に,実際の場面を想定して話す場を設定した。そこでは,幼稚園児ならどう反応するかを想定して,話す内容や話し方を検討している姿が見られた。このような活動を通して,よりよく伝えようとする思いが強まり,次時の学習に向けて意欲が高まったのではないかと考える。 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| イ |
第2次第③時 (本時) に関する考察 幼稚園児を前にすると,児童は,喜びを体で表現したり真剣な表情になったりした。実際に幼稚園児を前にしたことで,より明確に相手を意識し,学習意欲が高まったと考える。 実際に操作しながら話す活動の場面では,どのグル-プにおいても,児童は各自のめあてを基に熱心に話していた。そこでは,右の写真にあるように,対面して1対1で教えている姿が多く見られた。中には,一人で話すことにかなり抵抗のある児童もおり,その児童には 「お友達と二人で教えてあげよう。」と助言すると,安心したように話し始めた。 このように,児童2対幼稚園児1であったり,児童1対幼稚園児が数人であったりと,学習形態を多様にしたことにより,話しやすい場をつくることができたものと考えている。 また,前時に具体的な言葉を使って話す練習をしていた児童には, 「それとかあれという言葉を,何のことか分かるようにお話してごらん。」 と助言した。児童は 「お箸を持つ方から上げる」「お父さん指にかける」 など,具体的に話すことができるようになった。 自己主張の強い児童が,相手の反応を受け止めずに話し続けてしまい,幼稚園児に敬遠される場面も見られた。むしろ,口ごもりながらも,相手の反応を見ながら話す方が幼稚園児は耳を傾けていた。この場では,積極的に話すことも必要であるが,間をおくことや丁寧に話すことについての指導の重要性を実感した。 資料2は,児童の話と幼稚園児の反応である。ここでは児童が,竹とんぼは三回転させて放すことを教えている。それに対して幼稚園児が,一回転で放しても飛ぶことを主張している。教えている児童は,幼稚園児の考えを受け入れた上で,さらに話していることが分かる。 このように,教える立場であっても,相手の反応を共感的に受け止めようとすることこそが重要になってくる。相手の思いを認めてこそ対話が進むことになり,児童は話す楽しさが実感できると考える。 学習が進むにつれて,児童は,遊び方を覚えた幼稚園児に拍手を送ったり,他のグル-プに移動したりして教えていた。 終末段階では,幼稚園児からの感謝の言葉に,どの児童も満足した表情を浮かべていた。 資料3は,児童の感想をまとめたものである。自己評価カ-ドでも同様の感想がみられた。話すことが楽しいという思いと ともに,伝わる喜びや話すこと に関しての自分自身の成長に気付くことができたと考える。 |
||||||||||||||||||
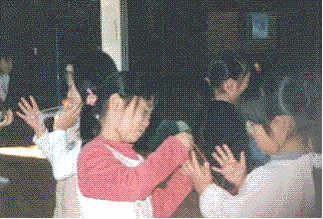 幼稚園児に教えている様子 |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ウ |
単元全体の考察 本研究では,国語科の学習と生活科の学習とを関連させることにより,実践と結び付いた音声言語の学習を成立させることができた。一人一人が言語活動のめあてを立てる場を設定したことも,児童が明確に目的意識をもって学習するために有効であったと考える。 また,伝承遊びを題材に採り上げたことにより,祖父母から伝わったことを幼稚園児に伝えるという一連の学習に必要感が生まれ,主体的な学習態度を持続させたと考えている。そこでは,児童は幼稚園児に伝えることで,伝えることの楽しさを実感し,よりよく話そうとする意欲をもつことができた。そのことが,まとまった話をしようとする意欲を喚起し,発声や口形など技能的な面も高めようとする意識をもつことができたと考える。 本実践は,児童が国語科で学んだことを即時に生活の中に生かしていくためには,話すことの実践の場を数多く設定することであると実感させられた試みであった。ここでの課題を踏まえ,今後も音声言語の学習について研究を進めていきたい。 |
||||||||||||||||||
[目次へ]