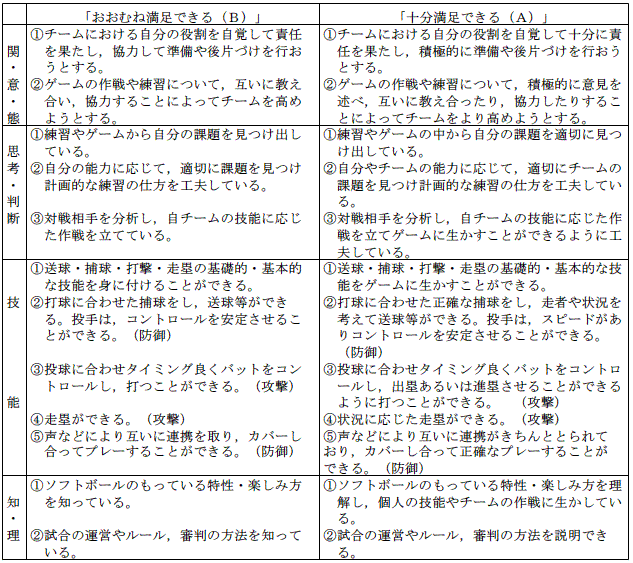| 【授業研究3】 |
| |
高等学校第1学年「球技」(ソフトボール)の指導 |
| |
| (1) |
主題に迫るための指導の手だて |
| |
ソフトボールは,社会体育でも盛んに行われており,一般的に親しみ易いスポーツであるとともに,ゲームの行い方を工夫することによって,個々の能力に応じた楽しみ方ができ,生涯にわたりスポーツに積極的にかかわるきっかけになるスポーツである。また,集団的スポーツの中でも個の役割が明確になるスポーツであり,プレーが1プレーずつ切れるために,状況に応じた作戦などを考えやすい種目である。このような特性を踏まえ,ソフトボールの授業を行った。
授業では,練習やゲームを通して個人の技能を高めていくとともに,自分のチームの特長を的確にとらえ,練習したことが試合に生きてくるようにグループで作戦を工夫させることを目標とした。また,相手チームを分析する能力も身に付けさせ,作戦で相手に勝利する喜び,楽しさを味わわせたいと考える。その指導の手だてとして次のようなことを工夫した。 |
| |
ア |
学習過程の工夫 |
| |
|
(ア) |
生徒の技能差が大きいという実態から,ねらい1では,今もっている力で攻撃を中心としたゲームを楽しみながら基礎的・基本的な技能や意欲の向上を目指した。ねらい2では身に付いた技能を生かし,グループとしての戦い方を工夫する楽しさを味わわせたいと考え,対戦チームに応じた作戦で,正規のソフトボールを楽しむ学習過程を設定した。 |
| |
|
(イ) |
1単位時間の学習過程では,練習とゲームを交互に実施し,自分の技量を伸ばすとともにチームの特長についてもとらえさせ,ゲームで不足している個人的技能や集団的技能を次時の課題として設定できるようにした。さらに,時間のはじめに,チームでのミーティングの時間を設定し,相手チームの分析や自チームの特長を生かした作戦を考えさせた。 |
| |
イ |
ルールの工夫 |
| |
|
ねらい1で,現在の自分たちの力量に応じたルールを生徒自身に工夫させて練習やゲームを行い,生徒の学習意欲を高めていきたいと考え,次のようなルールを提示し,生徒に選択させた。そして,それを基に新たなルールを工夫させたいと考えた。 |
| |
|
○ |
味方がピッチャーを行うゲーム |
| |
|
○ |
打者一巡によるゲーム |
| |
|
○ |
投手なしでのゲーム(ティーバッティングのゲーム) |
| |
|
○ |
スローピッチルールで2アウト制のゲーム |
| |
ウ |
グループ編成の工夫 |
| |
|
(ア) |
野球経験者をリーダーとしグループ編成を行った。リーダーが中心となり,練習計画を立案させた。 |
| |
|
(イ) |
簡易ゲームの中で個々の技能の状況を見て,グループ間の力量が等しくなるようにチーム編成を行った。 |
| |
エ |
資料の工夫 |
| |
|
(ア) |
学習カードに毎時間,「練習における意識・態度」,「練習における技能」,「試合における意識・態度」,「試合における技能」を記録させることにより自己の課題やチームの課題に気付かせた。さらに,その結果を基に次時の指導の改善を図っていった。 |
| |
|
(イ) |
学習カードの中で試合毎に打率,打点を記録させ,集計結果を生徒に提示し意欲を向上させた。また,自チームや相手チームの分析をする資料とさせた。 |
| |
| (2) |
授業の実際 |
| |
| 1 |
生徒の実態(男子32名) |
| |
○ |
メディアを通して目に触れることが多い野球型のゲームなので経験者未経験者を問わず関心意欲が高い。 |
| |
○ |
野球経験者が32名中8名とクラス4分の1をしめる。 |
| |
○ |
野球経験者と未経験者との技能の差が著しく大きい。 |
| |
● |
ボールをキャッチし,スローイングする動作がうまくいかない生徒が多い。 |
| |
● |
バットにボールが当たらない生徒が数名いる。 |
| |
○ |
ゲームの仕方や簡単なルールについては,ほとんどの生徒が理解できている。 |
| 2 |
学習のねらい |
| |
・ |
チームで協力し合い,力いっぱい相手チームに挑戦しゲームを楽しもうとする。 |
| |
|
(関心・意欲・態度) |
| |
・ |
チームで協力し合い,課題を決め,課題解決のために作戦を立てたり,練習方法を工夫したり,場の工夫をしたりすることができる。 |
| |
|
(思考・判断) |
| |
・ |
打ちやすいボールを見極め,ボールをバットに当てて出塁・進塁させることができる。 |
| |
|
(技能) |
| |
・ |
ボールを確実に捕球したり,ねらった場所に的確に送球することができる。 |
| |
|
(技能) |
| |
・ |
ソフトボールの特性やルールを理解することができる。 |
| |
|
(知識・理解) |
| 3 |
単元の学習活動における具体の評価規準 |
| |
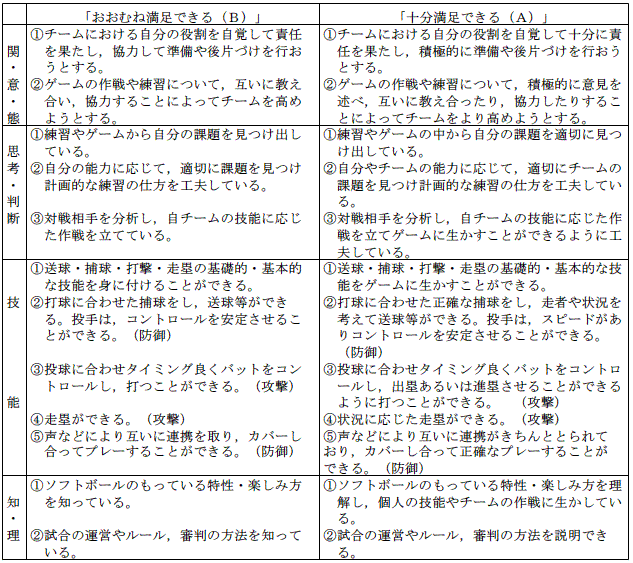 |
| 4 |
単元の学習の展開 |
| |
 |
|
| |
| (3) |
結果と考察 |
| |
ア |
グループ編成の工夫 |
| |
|
練習では,野球経験者がリーダーとなり練習計画の立案や,実際の練習の場でグループをリードし,良い雰囲気の中で学習ができていた。試しのゲームで個々の技能を見てチームの力が等しくなるように編成したが,試合の結果を見ると偏りが出てしまった。 |
| |
イ |
学習過程の工夫 |
| |
|
学習過程において,二つのねらいを設定したが,これらは概ね達成できたと考えられる。ねらい1の段階では,打撃にポイントを置いたゲームをすることで生徒たちは楽しさを感じ,休み時間にも練習するようになるなど,生徒はソフトボールに意欲的に取り組んでいた。また,勝敗に対する意識も高まり,ねらい2の段階になると努力を要する状況にある生徒でもバントをやったりヒットエンドランをやったりチームの作戦に応じた攻撃ができるようになった。また,各チームごとに守備隊形を工夫するなど,作戦の工夫がいろいろと見られるようになった。 |
| |
ウ |
ルールの工夫 |
| |
|
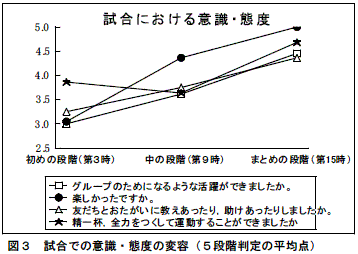 ねらい1において例示したルールは,一般的に行われているルールと違い,打撃を容易にするものであったため,生徒たちが十分楽しめるものであった。また,技能の向上を実感し,意欲も向上した。しかし,必要感をもてなかったためか,それをさらに工夫するという姿は見られなかった。
ねらい1において例示したルールは,一般的に行われているルールと違い,打撃を容易にするものであったため,生徒たちが十分楽しめるものであった。また,技能の向上を実感し,意欲も向上した。しかし,必要感をもてなかったためか,それをさらに工夫するという姿は見られなかった。 |
| |
エ |
資料の工夫 |
| |
|
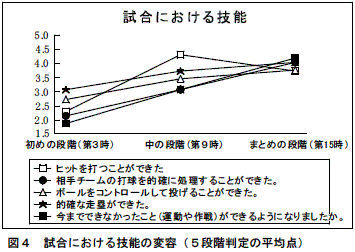 学習カードや自己評価表を記録することが,自己の課題やチームの課題を見つけ出すことに役立っていた。打率,打点の集計結果を提示したことは,チーム分析に役立ち,作戦に生かされていた。さらに,記録の向上を意識し,生徒が試合に取り組む姿勢にも変化がみられ,競争意識が個人の技能のレベルアップへとつながった。
学習カードや自己評価表を記録することが,自己の課題やチームの課題を見つけ出すことに役立っていた。打率,打点の集計結果を提示したことは,チーム分析に役立ち,作戦に生かされていた。さらに,記録の向上を意識し,生徒が試合に取り組む姿勢にも変化がみられ,競争意識が個人の技能のレベルアップへとつながった。 |
| |
オ |
自己評価の変容から見た考察 |
| |
|
 図5のように練習における技能及び意識・態度,試合における技能及び意識・態度の四つについて,その自己評価の変容の様子を見てみると,時間の経過とともに大きな伸びが見られた。このことについては,チームの中で個の技能のレベルアップを図ることが態度の変容をもたらし,態度の変容がさらに個のレベルアップにつながったのではないかと推測される。今回実施したソフトボールの授業では,①「ゲームの中で個の役割を課題として明確にもつことができた。」②「自分のグループにいかに貢献したかを生徒一人一人が意識することができた。」③「グループの中の役割を果たせるだけの技能をグループ練習で身に付けることができた。」と三つの点で成果が見られ,そのため,まとめの自己評価で「試合における意識・態度」の中の「楽しかった」に全員が5点満点をつけることができたと感じている。
図5のように練習における技能及び意識・態度,試合における技能及び意識・態度の四つについて,その自己評価の変容の様子を見てみると,時間の経過とともに大きな伸びが見られた。このことについては,チームの中で個の技能のレベルアップを図ることが態度の変容をもたらし,態度の変容がさらに個のレベルアップにつながったのではないかと推測される。今回実施したソフトボールの授業では,①「ゲームの中で個の役割を課題として明確にもつことができた。」②「自分のグループにいかに貢献したかを生徒一人一人が意識することができた。」③「グループの中の役割を果たせるだけの技能をグループ練習で身に付けることができた。」と三つの点で成果が見られ,そのため,まとめの自己評価で「試合における意識・態度」の中の「楽しかった」に全員が5点満点をつけることができたと感じている。 |
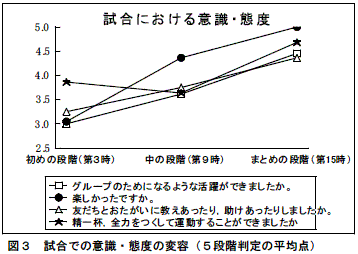 ねらい1において例示したルールは,一般的に行われているルールと違い,打撃を容易にするものであったため,生徒たちが十分楽しめるものであった。また,技能の向上を実感し,意欲も向上した。しかし,必要感をもてなかったためか,それをさらに工夫するという姿は見られなかった。
ねらい1において例示したルールは,一般的に行われているルールと違い,打撃を容易にするものであったため,生徒たちが十分楽しめるものであった。また,技能の向上を実感し,意欲も向上した。しかし,必要感をもてなかったためか,それをさらに工夫するという姿は見られなかった。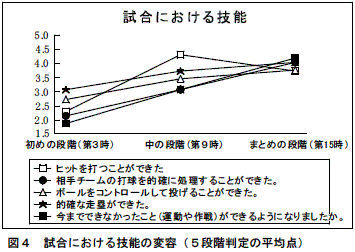 学習カードや自己評価表を記録することが,自己の課題やチームの課題を見つけ出すことに役立っていた。打率,打点の集計結果を提示したことは,チーム分析に役立ち,作戦に生かされていた。さらに,記録の向上を意識し,生徒が試合に取り組む姿勢にも変化がみられ,競争意識が個人の技能のレベルアップへとつながった。
学習カードや自己評価表を記録することが,自己の課題やチームの課題を見つけ出すことに役立っていた。打率,打点の集計結果を提示したことは,チーム分析に役立ち,作戦に生かされていた。さらに,記録の向上を意識し,生徒が試合に取り組む姿勢にも変化がみられ,競争意識が個人の技能のレベルアップへとつながった。 図5のように練習における技能及び意識・態度,試合における技能及び意識・態度の四つについて,その自己評価の変容の様子を見てみると,時間の経過とともに大きな伸びが見られた。このことについては,チームの中で個の技能のレベルアップを図ることが態度の変容をもたらし,態度の変容がさらに個のレベルアップにつながったのではないかと推測される。今回実施したソフトボールの授業では,①「ゲームの中で個の役割を課題として明確にもつことができた。」②「自分のグループにいかに貢献したかを生徒一人一人が意識することができた。」③「グループの中の役割を果たせるだけの技能をグループ練習で身に付けることができた。」と三つの点で成果が見られ,そのため,まとめの自己評価で「試合における意識・態度」の中の「楽しかった」に全員が5点満点をつけることができたと感じている。
図5のように練習における技能及び意識・態度,試合における技能及び意識・態度の四つについて,その自己評価の変容の様子を見てみると,時間の経過とともに大きな伸びが見られた。このことについては,チームの中で個の技能のレベルアップを図ることが態度の変容をもたらし,態度の変容がさらに個のレベルアップにつながったのではないかと推測される。今回実施したソフトボールの授業では,①「ゲームの中で個の役割を課題として明確にもつことができた。」②「自分のグループにいかに貢献したかを生徒一人一人が意識することができた。」③「グループの中の役割を果たせるだけの技能をグループ練習で身に付けることができた。」と三つの点で成果が見られ,そのため,まとめの自己評価で「試合における意識・態度」の中の「楽しかった」に全員が5点満点をつけることができたと感じている。