| 1 |
主題に迫るための指導の手だて |
| |
(1) |
教材の精選 |
| |
|
未習教材であるフラッグフットボールを実践することで,次のような点が期待できる。 |
| |
|
ア |
児童たちは,フラッグボールに対する経験が無いため,技術面では同じスタートラインからの学習ができる。 |
| |
|
イ |
ゲームでは,作戦を立ててプレーするため,一人一人の役割が明確になる。 |
| |
|
ウ |
作戦立案段階で,運動能力の低い児童も,その能力に応じて生かされる場をつくることができる。 |
| |
|
エ |
少人数でゲームを実施することで,運動の質や量が高まる。 |
| |
(2) |
学習過程の工夫 |
| |
|
ア |
作戦立案や作戦遂行に向けての集団的思考場面を設けた。 |
| |
|
イ |
ドリルゲームや課題ゲームを設け,基礎的・基本的な技能の習得や戦術的学習が,ゲーム感覚でみんなで楽しく学習できるようにした。 |
| |
|
ウ |
ねらい1(基礎的・基本的な技能や作戦の習得),ねらい2(チームの特長に応じた作戦によるゲーム)の発展的学習過程を設定し,個から集団への発展が段階的に進むようにした。 |
| |
(3) |
指導上の工夫 |
| |
|
ア |
個々に対する言葉かけを工夫した。(個々のねらいに応じて肯定的な言葉かけを多用し,学習意欲を高める。「前よりもこんなところが良くなったね」等) |
| |
|
イ |
形成的授業評価を実施し.次時の指導や支援に役立てた。 |
| |
|
ウ |
学習中,仲間に対する文句や非難をルールとして禁止し,肯定的な雰囲気の中で学習できるようにした。 |
| |
(4) |
資料の工夫 |
| |
|
ア |
学習の手引き(学習の流れ,ドリルゲーム,課題ゲームの内容,基本ルール等を示した)を作成したり,学習カード(振り返りカード)を活用したりした。 |
| |
|
イ |
基本的な作戦例を提示し,作戦立案を支援した。 |
| |
|
ウ |
フラッグフットボールのデモテープやVTRを活用した。 |
| 2 |
学習の道すじ |
| |
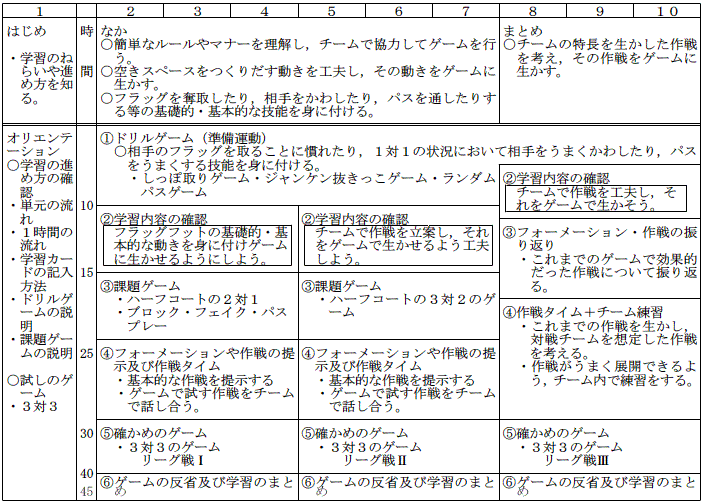 |
| 3 |
授業の結果と考察 |
| |
(1) |
教材の精選 |
| |
|
本実践で取り上げたフラッグフットボールは,児童たちにとって初めて学習するボール運動であったため,苦手意識をもつことなく取り組むことができた。ボールを操作する技術も簡単で,運動の苦手な児童にも受け入れられた。ゲームでは,3人のプレーヤーすべてに大切な役割が与えられ,それぞれが役割を果たすことによって作戦が成功する。そのため,協力して意欲的に練習やゲームに取り組むことができた。 |
| |
(2) |
学習過程の工夫 |
| |
|
学習過程では,基礎的・基本的な技能の習得をねらったドリルゲームを行い,主ゲームに必要な技能を楽しみながら確実に身に付けることができた。また,課題ゲームでは,自分たちの考えた作戦をどう実践したらよいか,また,失敗した作戦のどこが悪かったかについて話し合う等の集団的思考場面をしっかり確保することができた。 |
| |
(3) |
指導上の工夫 |
| |
|
場面に応じた言葉かけでは,その内容を矯正的なものと励まし・賞賛的なものを意識して使い分けた。また,名前を呼んだり肩をたたいたりして注意を引いてから行ったので,意識的に聞くようになり,学習に有効であった。 |
| |
(4) |
資料の工夫 |
| |
|
学習の手引きやデモテープ,VTRを活用したことで,動きのイメージや学習の道すじがとらえられ,効果的な学習が進められた。また,作戦の立案段階で基本的な作戦例を提示したことは,作戦づくりの話合いに有効だった。 |