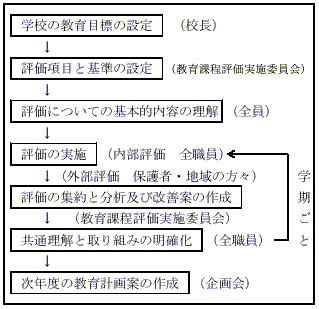| |
実践事例7 |
| |
小規模校の特性を生かした教育課程経営 |
| |
高萩市立君田中学校 |
| 1 |
教育課程経営の重点 |
| |
本校は,市街地から北西へ21km離れた標高516mの山間部に位置し,創立52年目を迎える。生徒数は23人,3学級の小規模校である。学校の教育目標「自らの力でたくましく生きる心豊かな生徒の育成」達成のための重点課題として「一人一人によりそった教育」と「自然環境を重視した体験教育の充実」をあげている。これを受け,教育課程経営では「小規模校の特性を生かした教育課程経営」を研究主題に掲げ,次の内容について,特に重点的に研究を進めている。 |
| |
| ○ |
教育課程評価の組織と教育課程の実施及び改善 |
| ○ |
個に応じた学習指導の工夫改善 |
| ○ |
地域に開かれた学校づくりの推進と外部評価の導入 |
|
|
| 2 |
教育課程経営の実際 |
| |
(1) |
教育課程評価の組織と教育課程の実施及び改善 |
| |
|
① |
教育課程評価実施委員会の取り組み |
| |
|
|
評価を進めるにあたっては,校長,教頭,教務部(3人)を中心に,教育課程評価実施委員会を設置し,評価の計画づくり,評価の実施と分析,学校改善案の検討等を実施する。
図1 1年間の評価の流れエ調査用紙の作成
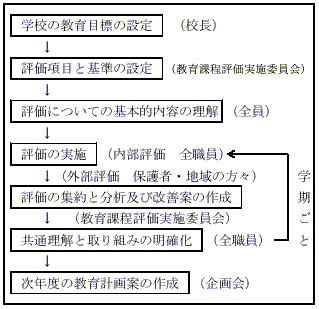 |
| |
|
|
ア |
組織づくり,評価方法,実施に関する原案作成 |
| |
|
|
イ |
外部評価の基本構想や実施計画に関する外部への広報活動 |
| |
|
|
ウ |
記録資料の収集と形成的な評価の実施 |
| |
|
|
エ |
調査用紙の作成 |
| |
|
|
オ |
評価の集約・分析と問題点の明確化 |
| |
|
|
カ |
各分掌からの改善案の集約 |
| |
|
|
キ |
各改善案の分類と検討 |
| |
|
|
|
・ |
緊急の改善策を講じる必要のある事項 |
| |
|
|
|
・ |
中期,長期にわたって改善していく事項 |
| |
|
|
ク |
再提示,再評価と最終改善案 |
| |
|
|
ケ |
次年度の改善事項についての報告 |
| |
|
② |
教育課程の実施・改善に当たって |
| |
|
|
ア |
学校の教育目標に照らして,日常の教育活動を随時評価し,諸条件の整理及び改善を図る(形成的評価の重視)。 |
| |
|
|
イ |
学期ごとに評価するが,特に課題と考えられる点については月ごとに評価し,年度内に改善できることは,積極的に改善し,学校環境・学習環境を整えていく。 |
| |
|
|
ウ |
学校行事の評価では,その都度気づいたことや改善策を記入してもらい,ファイルして保管する。次年度の取り組みに対する検討資料とする。 |
| |
|
|
エ |
改善案を検討するに当たっては, ( 各係が具体的な改善案を提示してから検討に入る特に長期の改善事項を明確にする)。 |
| |
|
|
オ |
改善のための話し合いの時間確保という点から,小グループによる検討の時間を多くとる(週案の調整によって生み出した時間も有効に使う)。 |
| |
|
③ |
教育課程実施上の工夫 |
| |
|
|
ア |
各週ごとの週時程計画による週案の作成と弾力的運用 |
| |
|
|
|
(ア) |
自習にしないような週案の作成・提示による各教科の授業時数の確保 |
| |
|
|
|
(イ) |
各教科の担当から出された要望を生かして,異教科担当者によるティーム・ティーチングを実施したり,教科の進度に応じたまとめ取りの工夫をする。 |
| |
|
|
イ |
朝の読書の時間の設定 |
| |
|
|
ウ |
職員朝会を減らし生徒と接する時間の確保 |
| |
|
|
エ |
生徒主体の体験活動の推進と時間の確保 |
| |
|
|
|
(ア) |
生徒の各行事での準備期間の位置付けと内容の検討 |
| |
|
|
|
(イ) |
事前学習会等での話し合い活動の重視(クリーン週間,緑を愛する少年隊活動,自然生産活動,公民館清掃,全生徒による生徒会新聞づくり) |
| |
|
|
オ |
学級担任二人制によるよりよい学級づくり |
| |
|
|
|
(ア) |
担任の生徒へのかかわり方を明確化し,生徒の内面の理解に努める。 |
| |
|
|
カ |
総合的な学習の時間「山びこ学習」の取り組み(年間85時間実施)
縦割りの形態を生かした個別課題の追究と学年指定課題(体験活動)の追究 |
| |
|
|
|
(ア) |
個別課題の追究 |
| |
|
|
|
|
| ・ |
生徒の興味・関心に応じた課題別に,学年の発達段階を加味しつつ,学年の枠にとらわれない縦割りの小グループを編成する。 |
| ・ |
全職員を各グループの支援者として割り振る。 |
|
| |
|
|
|
(イ) |
学年課題の追究 |
| |
|
|
|
|
| ・ |
本年度より取り組んだ自然生産活動。第1学年:愛鳥活動(巣箱づくり,給餌台づくり,探鳥会),第2学年:炭焼き活動(炭窯,ドラム缶による炭焼き,木酢液の採取と利用),第3学年:椎茸栽培活動(椎茸,なめこの栽培管理) |
| ・ |
各学年で事前学習会の準備計画や当日の計画を立て,全校で体験活動を実施する。
同時に各学年で課題を設定し,課題追究する。 |
|
| |
(2) |
個に応じた学習指導の工夫改善 |
| |
|
① |
少人数のメリットを最大限に生かす取り組み |
| |
|
|
ア |
基礎・基本の確実な定着 |
| |
|
|
|
(ア) |
学習習慣の定着という点から,各教科「自主学習のすすめ」の改訂版の作成 |
| |
|
|
|
|
| ・ |
活用に当たっての各教科ごとのガイダンスの導入 |
| ・ |
課題解決のためのアンケート調査の実施 |
|
| |
|
|
イ |
放課後の時間を活用した補充的な学習の推進 |
| |
|
|
|
(ア) |
生徒による学習相談表の活用 |
| |
|
|
|
(イ) |
放課後の質問時間の設定 |
| |
|
|
ウ |
各教科ごとの生徒の個別課題の設定と評価の蓄積化 |
| |
|
|
|
(ア) |
生徒一人一人の学習課題の明確化 |
| |
|
|
|
(イ) |
興味・関心,意欲,知的好奇心,やる気の引き出し方 |
| |
|
|
エ |
ティーム・ティーチング,ゲストティーチャーとの授業,学校図書館,コンピュータ等を活用し,個に応じたきめ細かい指導の工夫 |
| |
|
|
オ |
全職員の授業研修の推進と分析 |
| |
|
|
カ |
生徒の興味・関心に基づいた生徒の第一希望による選択教科の開設 |
| |
|
② |
ねらいに合った学習形態やティーム・ティーチングを生かした指導及びその研修 |
| |
|
|
ア |
単元に応じた異教科教師とのティーム・ティーチングの実施 |
| |
|
|
イ |
君田小・中学校職員によるティーム・ティーチングの実施 |
| |
|
|
|
(ア) |
週1回の小学校音楽科の授業におけるティーム・ティーチングの位置付け |
| |
|
|
|
(イ) |
児童数・生徒数減少による地区音楽会の合同発表会に向けての準備 |
| |
|
|
|
(ウ) |
縦割り学習,全校合同学習の導入 |
| |
|
③ |
君田小・中学校の授業研修の実施 |
| |
|
|
ア |
相互研修による系統的学習指導法の研修 |
| |
|
|
イ |
生徒数減少による複式学級に向けた研修 |
| |
(3) |
地域に開かれた学校づくりの推進と外部評価の導入 |
| |
|
① |
開かれた学校づくりのための地域人材の積極的な活用 |
| |
|
|
ア |
ボランティア活動への参加の呼びかけ |
| |
|
|
|
(ア) |
専門性・特技を生かした参加登録〔山びこ学習(愛鳥活動,炭焼き活動,椎茸栽培活動),各教科等新たな体験活動のための地域人材の参加〕 |
| |
|
|
|
(イ) |
技術面で常時アドバイスをもらうために地域人材の活用を図る。 |
| |
|
|
イ |
特技を生かした教育環境整備 |
| |
|
|
|
(ア) |
作業小屋,炭窯,堆肥箱,広場のテーブル等教育環境施設等の整備と補修 |
| |
|
|
|
(イ) |
PTA役員会を通した地域への呼びかけ |
| |
|
② |
広報活動の推進による家庭・地域への情報提供 |
| |
|
|
ア |
学校だよりの地域内商店への常時設置 |
| |
|
|
イ |
全世帯配布の生徒会新聞(生徒による配布から地域の回覧組織への利用変更) |
| |
|
③ |
生徒の減少を見込んでの改善 |
| |
|
|
ア |
保護者OB会の結成と教育活動への協力体制 |
| |
|
|
イ |
小・中学校合同委員会の設置の検討 |
| |
|
|
ウ |
小・中学校合同行事の内容検討と地域保護者参加行事の検討 |
| |
|
④ |
教師の持つ技能・知識の地域への提供(君田中趣味の講座の開設) |
| |
|
|
ア |
教師の空き時間を利用した講座開設と地域の方・生徒参加による講座検討 |
| |
|
⑤ |
外部評価の導入(教育活動全般にかかわる評価:主に保護者等による学校評価) |
| |
|
|
ア |
外部評価の導入に向けて |
| |
|
|
|
(ア) |
学校・家庭・地域等の情報交換を活発にする。 |
| |
|
|
|
|
| ・ |
地域一体となった行事と地域の方の声の収集及び双方からの情報発信 |
|
| |
|
|
|
(イ) |
地域の方の学校教育理解のために学校への来校を推進する。 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
(ウ) |
結果をどう生かしていくかを説明し,理解を得ることができるようにする。 |
| |
|
|
イ |
具体的な外部評価の方法とその生かし方 |
| |
|
|
|
(ア) |
地域との協力体制が比較的確立し,地域から意見がもらえるので,これまでの取り組みを大事にする。 |
| |
|
|
|
(イ) |
校務分掌組織のどの部分を使うのかを明確にする。 |
| |
|
|
|
(ウ) |
外部評価の目的,内容,方法などを明確にする。 |
| |
|
|
|
|
表1 外部の声を反映する方法
 |
| 3 |
今後の課題 |
| |
(1) |
教育課程経営の改善のための組織を工夫し,より有効な改善方法を見い出すこと。 |
| |
(2) |
「開かれた学校づくり」「特色ある学校づくり」のために,内部評価と外部評価とのよりよい関連の在り方を明らかにすること。 |