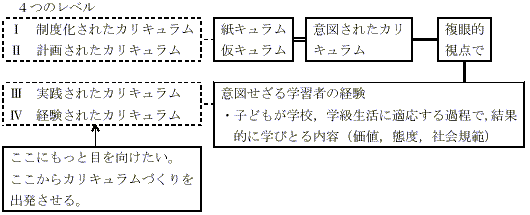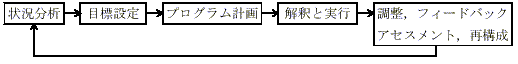| 第2 理論研究 |
| |
筑波大学教授田中統治先生を講師に招き,2回の講義を受け,理論研究を進めてきた。 |
| 1 |
平成13年度の講義概要 |
| |
講義題「特色ある学校づくりとこれからの教育課程の編成」 |
| |
(1) |
教育課程からカリキュラムへ |
| |
|
① |
カリキュラムの思想と概念 |
| |
|
|
ア |
教育課程=教育行政的とらえ方からの転換 |
| |
|
|
|
・ |
カリキュラムは,研究のための概念であり,組織の思想を背景にもつ。 |
| |
|
|
|
・ |
これまでは紙(カミ)キュラム(紙の上に書かれた教育計画,教育課程表,時間割),つまり文書化された教育課程であって,学ばれた内容に注目してこなかった。 |
| |
|
|
|
・ |
語源 ラテン語 currere(クレレ:走る)・・・競走路→学習の筋道→学習経験 |
| |
|
|
|
・ |
児童生徒が学ぶ内容そのものに注目すること,学習経験の総体としてのカリキュラム |
| |
|
|
イ |
カリキュラムという視点によって教師の無関心を見直していく。 |
| |
|
|
|
・ |
学校内には学年・教科によるセクショナリズムが生じやすくなる。 |
| |
|
|
|
|
 |
| |
|
② |
カリキュラムの位相とその開発 |
| |
|
|
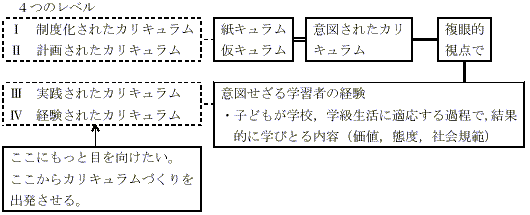 |
| |
(2) |
カリキュラムづくりのための理論と視点 |
| |
|
 |
| |
(3) |
校内カリキュラムセンターの実践 |
| |
|
① |
教師への支援のシステム化 |
| |
|
|
ア |
学校にカリキュラムを統括するシステムをつくる。 |
| |
|
|
イ |
カリキュラム開発は学校経営の中心である。
| 各学校が「足元」をよく見る |
・・・ |
説明責任を果たすためにも,足場を固めることが大切である。 |
|
| |
|
② |
カリキュラムマネジメントの技能の向上 |
| |
|
|
ア |
| カリキュラムの作成 |
・・・ |
全職員,児童生徒,保護者,地域の人々のニーズまでとり入れる視野の広さが求められる。 |
|
| |
|
|
イ |
校長の役割 |
| |
|
|
|
(ア) |
教員にやる気を起こさせ,カリキュラムづくりの先頭に立つ。 |
| |
|
|
|
(イ) |
カリキュラムづくりはトップダウン方式のみでなくボトムアップ方式の気運をつくることである。 |
| |
(4) |
カリキュラム評価の実践 |
| |
|
① |
調査としてのカリキュラム評価 |
| |
|
|
ア |
評価をする前にまずデータ集めを:「論より証拠を」 |
| |
|
|
|
(ア) |
教師はすぐに価値評価を行いがちである。 |
| |
|
|
|
(イ) |
良し悪しの評価をする前にデータの収集を行う。 |
| |
|
|
|
(ウ) |
テストの結果もデータの一つである。 |
| |
|
|
|
(エ) |
成果を急ぐのではなく,失敗から学びながら小さな成果を積み上げていく。 |
| |
|
|
イ |
アセスメント |
| |
|
|
|
(ア) |
学習者のニーズを発掘するための事前のアセスメント〔調査→データ化→議論(根拠をもとに)〕 |
| |
|
|
|
(イ) |
事後の効果を見るアセスメント〔調査→データ化→議論(根拠をもとに)〕 |
| |
|
|
ウ |
観察を基本とした自己点検を |
| |
|
|
|
(ア) |
教師の眼による観察法 |
| |
|
|
|
(イ) |
VTRによる振り返り・話し合い |
| |
|
|
|
(ウ) |
テストや質問紙による計量的な分析法 |
| |
|
② |
カリキュラム評価の利用 |
| |
|
|
ア |
今までの問題点を克服し学校に基礎をおくカリキュラムづくりを,これまで「カン」と「コツ」の世界の中で印象的に進めてきた傾向が強い。 |
| |
|
|
イ |
カリキュラム評価は,調査をし,データを収集し,それを根拠に議論するものである。これからは,「学校を基礎にしたカリキュラム開発」(School-Based Curriculum Development:SBCD)モデルを参考にして,学校教育の成果を具体的に示すことが求められる。 |
| |
|
|
|
SBCDのモデル
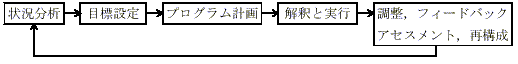 |