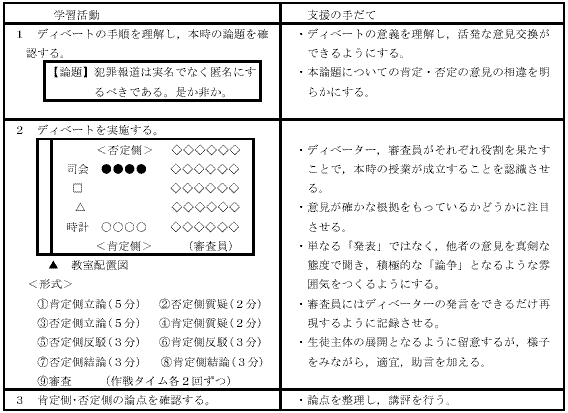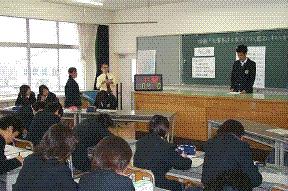| (1) |
授業の構想
本研究の研究主題は「豊かな表現力やコミュニケーション能力を育てる社会科学習の指導の在り方」である。この研究主題に迫るためには,生徒が自分なりの見方や考え方をもてるようにはたらきかけ,生徒が自分で調べたことや考えたことを適切な方法で表現する場を設定していくことが必要である。
本学習は,立場やルールをあらかじめ決めて討論するディベートという形式を取り入れ, 生徒相互の活発な論争を引き起こそうとするものである。いわゆる自由討論の場合,生徒の視野が狭く内容的に深まりが不十分になったり,論点が拡散したりで,思うように学習効果があがらない,ということをこれまでに経験してきた。そこで本学習では,自由討論ではなく,二つの立場が論争に発展しやすいような進行ルールをつくり,すぐに生徒が論争を始められるようにディベートというかたちをとることとする。
ディベートは本来,論争力を争う知的な「競技」であり,目標の中心は,論争技術を学び論争に勝つことである。したがって時折テレビ等で目にするディベートは,ただ相手の弱点を探してやり込めるだけに集中する傾向がある。しかし授業で行うディベートは,「競技」という面より「学習」という面を強調するように生徒を導いていかなければならない。つまり大切なのは論争自体が目的なのではなく,論争によって生じる学習効果が目的だということである。論争が争いであるかぎり勝ち負けが大きな要素となるが,勝つことのみを追求するのではなく,論争を通してクラスが「共同的に探究する」学習を深める必要がある。
つまり,ある論点に対して,ディベーターの生徒の発する肯定側の意見と否定側の意見が, それぞれ有力な根拠をもっていて,聴衆の生徒は肯定・否定両方の意見に説得力を感じ,その問題解決策について「迷い」をもつようになり,問題への関心の続くかぎり,よりよい問題解決策を探究する姿勢をもち続けるようになる。このような生徒の姿勢をはぐくむこともディベートを授業に導入する目的の一つである。
本ディベートにおいては,『犯罪報道は実名でなく匿名にするべきである。是か非か』を論題とする。近年,マス・メディアの実名報道によるプライバシーの侵害や名誉毀損の被害が著しい。しかしながら依然として事件報道は原則実名であるケースが多い。「実名か匿名か」という選択をめぐって,被害者と加害者の人権,報道の役割などの問題が論じられるであろう。これらの問題は,情報化社会の中で情報の価値が高まり,利益を得られることも不利益をこうむることもある,今日の私たちの生き方において,他者とのかかわりや社会の倫理基準について考察するきっかけとなるのではないかと考える。 |
| (2) |
指導の手だて
| ア |
自分なりの見方や考え方をもてるようにするための工夫
| (ア) |
多様な方法によって資料を収集する場の設定
本論題に関わる題材を扱った教科書や資料集の箇所以外に,図書館等にある書籍,インターネットなど,様々な方法で調べることができることを示す。必要があれば報道やマス・メディア論についての著作や学者を紹介し,調査活動を援助する。実際に,調査のための時間を授業中に設定したり,放課後等を用いたり積極的に調査活動をするように促す。そのうえで,調査した資料の受け売りではなく,しっかりとした根拠をもって意見を構築するようにはたらきかける。
ディベートというと論争の部分ばかりが強調されがちだが,論争に入る前の資料の収集など事前学習が重要である。それら入念な準備があってはじめて,活発な論争が可能になってくる。 |
| (イ) |
少人数グループでの意見交換の場の設定
ディベートで同じチームになった者は,それぞれ個人が調べ考えた意見を,互いに話したり聞いたりして,認識を深めていく。その際,多様な価値観や立場,状況の違いなど個人では気が付きにくいところにまで目を向けられるようにさせたい。また今回はディベーターではなく聴衆(審査員)となる生徒も,ディベーター同様,調査活動をし,論点を整理したうえで,聴衆となる生徒同士で意見交換をし,ディベート当日の審査に臨むように指導する。 |
|
| イ |
自分で調べたことや考えたことを適切な方法で表現する場を設定するための工夫
| (ア) |
ディベートの方法の理解
ディベートの方法(論題に対する肯定側と否定側のチーム編成,司会者・計時係・審査員の役割,論争のやりとりの手順など)を説明する。場合によっては,ディベーターは自分の主張と異なる立場に回ることもありえるし,審査員は自分の意見と判定を混同してはいけないことなどを注意する。あくまでディベートでは「論理性」や「主張の裏付け」を重要視することを心がけたい。 |
| (イ) |
立場の違いへの配慮
ディベートには二つの型がある。一つは資料の収集に大きく力を注ぎ,証拠を引用しながら論争を進めるもの。もう一つは,様々な立場から社会を捉え,その人の置かれている状況の違いが,どのような判断の相違につながるのかに思いをめぐらせながら論争を展開するもの。現代社会の授業におけるディベートは後者の側面が強く,多様な価値観や立場, 状況の存在を前提にして,それぞれの価値観や立場で同じ現状がどのように異なって評価されるのか,想像力によって自分のこととして考え,我々の社会がもつべき倫理基準を考えようとするものである。ディベートを通して,異なる立場に思いをめぐらせることの大切さを学ばせたい。 |
| (ウ) |
ディベートの実践
ディベートとはどういうものかを生徒に理解させるために,まずビデオを視聴したり,ウォームアップ・ディベートと名付けた簡単なディベートを実施する。ウォームアップ・ディベートとは,本を読んだり,その他の何かで調べなくても,チームで相談しさえすれば,すぐ論争が始まれるディベートのことである。たとえば「高校生には制服は不要である」という論題なら,生徒は自分の感性で意見を述べることができる。ウォームアップ・ディベートで訓練を積んだら,いよいよ本番である。 |
|
| ウ |
社会問題を探究し認識を深める姿勢を育成するための工夫
| (ア) |
ディベート後の意見のまとめ
ディベートを体験しつつ学ぶ過程で,生徒の意見がどのように変容するのかを把握する。まずアンケートによりディベートを意識しない段階での自然な意見を記録しておく。その後,論題についての調査活動を実施し,実践したディベートを振り返りながら,論題に関する自分なりの考察を加えて,事後レポートを書く。この作業を通して,生徒は自分の認識深化のプロセスを反省することができる。 |
| (イ) |
複眼的思考で認識を深めるはたらきかけ
ディベートを通して社会的な論争問題を正反対の二つの視点から分析することになるが,つまり,それは複眼的思考で社会を捉えることにつながる。社会には様々な異なった利害や価値判断があり,複雑な事実と価値の関係を総合的に分析・評価することが必要になってくる。ディベートにおける複眼的思考とは,社会問題の複雑さに総合的に立ち向かう実践的な思考であり,こうした見方で社会を分析できたときに,社会問題の認識が深まったと生徒は感じるのではないだろうか。 |
|
|
| (3) |
学習指導案
| ア |
学習活動計画
| 時 |
学習活動・内容 |
活動の支援 |
| 1 |
・ディベートの方法を理解する。 |
・「ディベート甲子園」のビデオを視聴させる。 |
| 2 |
・ディベートの練習をする。 |
・簡単なウォームアップ・ディベートを実施する |
| 3 |
・犯罪報道の問題点をまとめる。 |
・実例を挙げ,犯罪報道の問題点を認識できるようにする。 |
4
・
5 |
・実名報道と匿名報道の長所・
・短所をまとめる。
・「犯罪報道は実名でなく匿名に
するべきである。是か非か。」
を論題とするディベートに向
けて準備を進める。 |
・実名から匿名に移行したスウェーデンの例を取り上げたり,
様々な立場から考えさせるようにする。
・ディベーターの生徒は匿名報道の肯定・否定の各立場から,
確かな根拠をもった意見を述べられるように準備することを
指示する。
・ディベーターの生徒には,立論・質疑・反駁など本番を想定
し発表用原稿を作成するように助言する。
・審査員の生徒も,調査活動をし,論点を明らかにしておくよ
うに指示する。
・参考文献等を紹介し調査活動を援助する。
・生徒相互の意見の交換を促す。 |
6
本
時 |
・ディベートを実施する。 |
・論題に対し根拠のある論争が展開されるように注意する。
・他人の意見に耳を傾けさせるようにする。
・審査員が適正な判定を下せるようにする。 |
| 7 |
・自分の意見をまとめる。 |
・調査活動,ディベートを経験し,自分の意見がどのように
変容したか述べるように指示する。 |
|
| イ |
本時の学習
| (ア) |
本時の目標
| a |
有力な根拠を示しながら,犯罪報道における匿名報道の是非を論じ合い,立場や状況の違いがどう評価の違いを生み出すのかを理解する。 |
| b |
ディベートの要領を学び,論争を通して思考力を高め,社会における倫理基準について考察するきっかけとする。 |
|
| (イ) |
準備
立論資料(ディベーターが発表用に用意),記録用紙,審査用紙,掲示用進行表,時計(計時用) |
| (ウ) |
展開
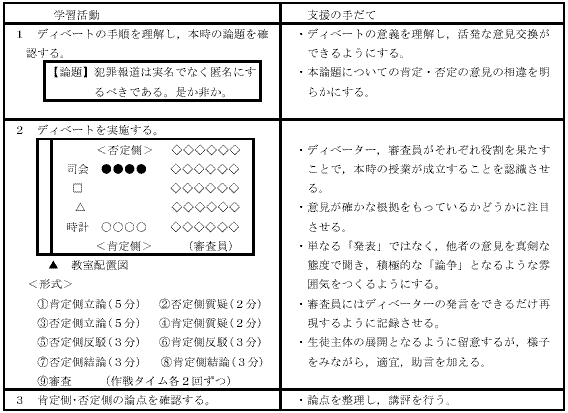 |
|
|
| (4) |
授業の考察
| ア |
自分なりの見方や考え方をもてるようにするための工夫
論争を行う前に,まずは確かな根拠をもった自分なりの考えをもつことが大切であるが,そのためには論題に関わる適切な資料の収集が重要になる。授業中に設定した調査活動の時間以外にも,放課後や自宅で積極的に書籍,インターネット等で資料の収集にあたる生徒もいて,生徒は概ね積極的に活動していた。ただし,ある立場からの意見のみを深く探究するあまり,異なった立場への配慮に欠ける場面も見られた。また事前のアンケートでは「実名報道ではかわいそう」とか「実名報道で懲らしめたほうがいい」というような意見もあったが,「感情」ではなく「論理」を根拠として意見をもつように促した結果,稚拙な情緒論は少なくなっていった。
さらに個人ごとの調査活動後,少人数での意見交換を指示したが,自分と異なる意見は刺激となり,同じ意見でも確認の意味があったようだ。自分だけでは気づきにくい問題点を知ったり,他者の意見をもとに,再び自分の意見を組み立て直したり,意義ある活動となった。
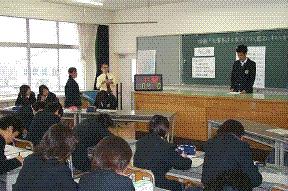
ディベートの様子
|
|
| イ |
自分で調べたことや考えたことを適切な方法で表現する場を設定するための工夫
最初に,ディベートとはどういうものかを説明したが,アンケートによると,中学の時に経験している者も多く,本学習を進めていくうえで心強く感じた。次に「ディベート甲子園97年中学決勝」のビデオを視聴させた。このビデオは中学生ではあるが,活発な論争が展開されており,ディベートの要領を生徒に理解させるのに適している。このビデオを視聴して,ディベートをやってみたいと思うようになった生徒が増えたようだ。
続いてウォームアップ・ディベートと名づけた簡単なディベートで「練習試合」を行った。最初はなかなか論争が活発化しなかったが,次第に意見が出るようになり,生徒によっては相手の意見に対して切り返しを見せるなど,要領を得るようになっていった。
本番では,肯定側と否定側の双方の立論の要旨を,事前に交換させておいたため,質疑や反ばくをあらかじめ想定しておくことができたとはいえ,期待以上の活発な論争が展開された。ディベーターの入念な下調べ・準備が大きな成果を上げたと言える。また審査員の生徒達が熱心に記録用紙にメモをとり,真しな態度で「参加」していたのには大いに感心した。ディベーターも審査員も役割を果たすことができ,様々な視点から社会を捉え, 異なる立場を理解し合う,良い機会になったのではないか。
資料1 ディベートの感想(審査員の感想から)
- 肯定側も否定側も,自分の考えをきちんともっていてすごいと思った。また,そのことをちゃんと自分の言葉にできているところがすごいと思った。みんな堂々としていた。
- どちらも素晴らしい論理展開であった。聞いていて納得させられることが多く,おもしろかった。
- みんなそれぞれ頑張っていて,よく調べてあって,びっくりした。はっきり伝えようとしているのがわかり,五分五分で勝敗の判定は難しかった。ディベート甲子園に出られると思った。
- 強調したいことを何度も繰り返したり,大きな声ではっきり言っていて聞き取りやすかった。
- 肯定側の結論が,自分達の言いたいことをズバリ言っていて,説得力があった。
|
|
| ウ |
社会問題を探究し認識を深める姿勢を育成するための工夫
ディベートを意識する前の事前アンケートとディベート後のレポートを読み比べてみると,生徒の認識の深まりを感じることができる。感覚や感情ではなく根拠に基づく論理性のある意見を述べることのできる生徒が増えた。
また,本学習の間,理論的なものの見方,異なる立場へ配慮した考え方,などの大切さを力説してきた。その結果,本学習を終えた生徒に「多面的に社会問題を分析し,様々な立場に思いをめぐらせたうえで,根拠のある自分の意見をもつ」という態度が身についたのではないかと考える。少なくとも,他者とのかかわりの中で社会の倫理基準を考えなければならないことを学んでくれたのではないか。 |