選択履修と「総合的な学習の時間」の在り方
― 個に応じた多様な学習活動をねらうS中学校の事例 ― |
| 1 |
研究のねらい |
| |
(1) |
選択教科の履修における生徒の課題追究の状況から実施上の配慮事項を明らかにする。 |
| |
(2) |
学校教育目標「力のある人間となれ」を具現化する「総合的な学習の時間」をいかに展開するかを明らかにする。 |
| |
|
| 2 |
基本的な考え方 |
| |
(1) |
選択教科の履修に充てる授業時数を最大限に設定し,生徒の主体的な学習を促進する。 |
| |
(2) |
「総合的な学習の時間」において学校で学んだ知識等を実感をもって理解できる機会を設ける。 |
| |
|
| 3 |
学校・地域の実態 |
| |
(1) |
学校の実態 (生徒数657人 20学級 教職員39人) |
| |
|
ア |
選択履修の拡大の継続研究の結果,生徒は多様な学習活動を創造するようになり,その学習要求に対応するため15人の社会人講師を招き,全職員で支援活動をしている。 |
| |
|
イ |
自ら課題を見付け,追究し続ける力を育てることが課題である。 |
| |
(2) |
地域の実態 |
| |
|
ア |
保護者の学校への要望は,学力の保障と子どもの楽しい学校生活が大半である。 |
| |
|
イ |
学区内に図書館など多数の公共機関や一級河川があり多数の文化人を輩出している。 |
| |
|
| 4 |
具体的な工夫 |
| |
(1) |
各教科,道徳,特別活動において,基礎・基本を確実に身に付けるための重点施策 |
| |
|
ア |
学習相談を充実する |
| |
|
イ |
個別指導やグループ別指導を充実し,テイーム・テイーチングを実施する。 |
| |
|
ウ |
体験的な学習,問題解決的な学習を重視する。 |
| |
|
エ |
コンピュータ等の教材・教具を積極的に活用する |
| |
(2) |
選択履修の拡大で,生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるようにする。 |
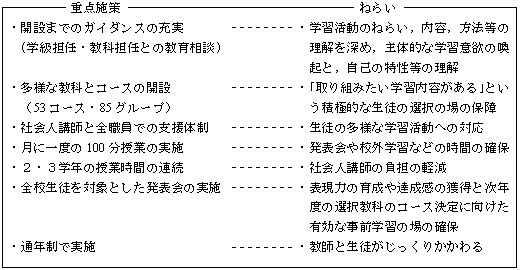 |
| |
(3) |
「総合的な学習の時間」で,生徒が社会とのかかわりの中で,自分自身の確立を目指す。 |
| |
|
ア |
生徒の主体的な問題意識や興味・関心を引き出すために |
| |
|
|
(ア) |
生徒と教師がじっくりと話し合い,生徒が自己の特性を見つめられるようにした。 |
| |
|
|
(イ) |
主課題や学年の課題を提案し,3年間の学習の見通しを持てるようにした。 |
| |
|
|
(ウ) |
選択教科の学習を充実し,関連させるように配慮した。 |
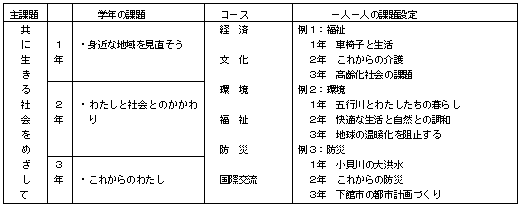 |
| |
|
イ |
「総合的な学習の時間」を確保するために |
| |
|
|
(ア) |
学び方や調べ方については,各教科が連携し,その特質に応じ重点的に指導した。 |
| |
|
|
(イ) |
学校裁量の時間を計画的に活用した。 |
| |
|
| 5 |
評価の工夫 |
| |
(1) |
意識・実態調査を各学期に2度実施し,生徒の変容を捉えた。 |
| |
(2) |
ワークシート,ノート,作文,絵,レポートなどの製作物,発表や話合いの様子学習活動の過程で使用したもの全てから一人一人の生徒の学習の姿を捉えた。 |
| |
(3) |
教師全員が協力して日常の学習活動の中での変化や出来事などを集積し保存することで生徒の悩み,工夫や努力,進歩・成長の様子を具体的に捉えた。 |
| |
|
| 6 |
成果と今後の課題 |
| |
(1) |
成果 |
| |
|
ア |
教師は,必修教科の授業改善を痛感するとともに,生徒と共に学ぶ姿勢で一人一人の学習要求に対応することが大切であることを実感した。 |
| |
|
イ |
生徒は,選択教科の履修や「総合的な学習の時間」で自分を試すことにより,基礎・基本の必要性に気付き,学び直しが始まり,主体的に学習に取り組むようになった。 |
| |
(2) |
今後の課題 |
| |
|
ア |
生徒が課題意識を持続し,追究過程における自己修正を可能とするために,ガイダンスを充実し,学習相談の在り方を工夫する。 |
| |
|
イ |
各生徒が課題追究から得られたものを持ち寄り,生徒相互が共に学び合い,広い視野から学習を深められるようにする。 |
| |
|
ウ |
生徒の情報の集め方やまとめ方等を学習の手引きとして毎年累積し,下級生の課題追究の手本とするとともに,よりよいものを創り上げようとする学習意欲を高める。 |