選択教科における魅力ある授業の展開
-「3つのフリー」の視点から選択100分授業に取り組むT中学校の事例- |
| 1 |
研究のねらい |
| |
(1) |
現行の教育課程における3年選択教科の授業を時間的・空間的・人的な面から再検討し,「生徒が楽しみにし待ち遠しくなる」ような魅力ある授業の実践を試みたい。 |
| |
(2) |
「自ら学ぶ力」を育て,学習過程や自己表現の場の工夫等を「総合的な学習の時間」にも生かしていく。 |
| |
|
| 2 |
基本的な考え方 |
| |
| |
学習への視点 |
キ-ワ-ド |
期待される学習 |
| タイムフリー |
学習時間100分
30分3サイクル学習 |
学習の継続,思考の深まり
探究活動, 問題解決学習の充実,弾力的運用 |
・生徒のニ-ズに基づく学習
・ゆとりのある学習
・試行錯誤のある学習 |
| スペイスフリー |
学習の場を地域へ |
町施設等の活用,地域の人との関わり,ニーズに応じた活動,特別教室の活用 |
・体験からスタ-トする学習
・学校以外からの情報収集
・人を通しての学習 |
| マンフリーー |
援助指導の充実
外部の指導者
評価の多様化
(賞賛・承認) |
T・T
地域人材を生かす
学習意欲の継続
ワ-クショップ |
・「本物に出会う」「人とふれあう」学習
・驚きや感動のある学習
・学びがいのある学習 |
|
| |
|
| 3 |
学校・地域の実態 |
| |
本校は23クラスの大規模校である。学校周辺には,福祉センタ-,老人ホ-ム,病院等 数多くの福祉施設があり,福祉に関する学習環境には恵まれている。
また,「生徒が主役の学校づくり」を展開し,生徒が学習や生活の場で成就感や達成感を 味わえるように努めている。部活動でも多くの成果を上げている。 |
| |
|
| 4 |
具体的な工夫 |
| |
(1) |
100 分の良さを生かした学習活動
(8クラス前後期制,2教科選択)
(前後期は10月末切替え) |
| |
(2) |
生徒のニ-ズ調査と生徒を引きつけるオリエンテーションの工夫 |
| |
(3) |
活動ファイルの活用 |
| |
(4) |
教師のアイディアを生かした魅力ある授業 |
| |
(5) |
「はっとする・感動する」体験 |
| |
(6) |
地域人材の適切な活用 |
| |
(7) |
人との関わりを通した調査活動や探究活動の実施 |
| |
(8) |
賞賛・承認・相互評価の場としてのワークショップの開催 |
【前期学習活動計画】
選択理科年間指導計画 コース:「なんでも実験トライアルコース」
| 第1~4 (2U) オリエンテーション 1Uは100分 |
| U |
月日 |
学習活動 |
活用人材 |
活用施設 |
| 3 |
5/28 |
プラネタリウム見学 |
|
| 4 |
6/10 |
何でも実験トライアル
※生徒が実験を選択し、グループにより活動する。
①鉄粉かいろをつくろう。(NHK)
②モーターをつくろう。
(東書理科おもしろ3実験・ものづくり完全マニュアルP.197)
③忍法!氷点の指でアイスクリームをつくろう。
④電球を作ってみよう。
⑤浴室と台所にある酸と塩基(丸善身近な化学実験1 P.170)
⑥電気パン焼き器(②と同じP.12)(新出出版 いきいき物理)
⑦電球の大きさを手がかりにして中和を調べよう(大日本下P.12)
⑧葉の標本づくり(②と同じP.274)
|
| 5 |
6/18 |
| 6 |
6/30 |
| 7 |
7/1 |
| 8 |
7/14 |
野外観察 |
G・T |
北山公園 |
| 9 |
9/8 |
⑨小麦粉を用いて酸化銅の還元(大日本P.117)
⑩なぜ回る、こまの不思議(NHK)
⑪ソーラーバルーン(②と同じP.94)
⑫いなづまをつくろう(東書1下P.17)
⑬簡単な楽器をつくろう(大日本上 P.49)
⑭紙で作るブーメラン、竹とんぼ(NHK)
⑮ペットボトルを利用したサイエンス(NHK)
⑯いろいろな電池をつくろう(東書1下P.108)
|
| 10 |
9/16 |
| 11 |
9/29 |
| 12 U 10/13 |
ワークショップ(まとめ、発表会) |
|
|
| 10/31 |
文化発表ワークショップ |
|
|
|
| |
|
| 5 |
評価の工夫 |
| |
(1) |
評価の観点 |
| |
|
ア |
自らの興味・関心に基づき,ゆとりをもって問題解決や探究活動に,主体的・創造的に取り組む学習活動が展開されているか。 |
| |
|
イ |
自ら学ぶ力が生徒に育っているか。 |
| |
|
ウ |
教師の授業に対する意識改革がなされているか。 |
| |
(2) |
評価の方法 |
| |
|
ア |
活動ファイルによる自己評価
生徒変容の定期的,継続的アンケ-ト調査 |
| |
|
イ |
授業の客観的な評価場面の設定
(選択授業参観,教科部員会等) |
| |
|
ウ |
ワ-クショップを開催しての生徒相互・教師・保護者等からの多面的評価 |
【文化祭でのワークショップの活動内容】
| 教科 |
ネーミング |
内容 |
| 国語 |
文豪屋敷 |
自作の小説や絵本の展示 |
| 社会 |
Enjoy place
“社会” |
縄文について(歴史・漁・暮らし・土器)・環境問題・福祉・自作笠間焼の展示・プロ野球の歴史・新撰組について・手話展示体験 |
| 数学 |
パズルランドへ
ようこそ!! |
ルービックキューブにチャレンジ タングラムに挑戦 空間図形に挑戦 コロンブスの卵・清少納言・知恵の板 |
| 理科 |
やってみよう
なんでも実験工房 |
びっくりコーナー(ゲッターピカイチ・ペットちゃんボトルちゃん)
おいしいコーナー(アイスやさん・ショックパンマン)
なるほどコーナー(回る回るコインの不思議・カイロ) |
| : |
: |
: |
|
| 【ワークショップにおける生徒の感想】 |
| |
|
- 保護者や先生が自分の作品を読んでくれたこと。お客さんが自分の作品を読んでくれた時、やりとげたなあと感じた。
- 制作過程、当日とも楽しく活動できた。自作の小説を真剣にに読んでくれた人がいたことが一番うれしかった。
- 自分で作った本などを読んでもらったことは本当にうれしかった。そのために一生懸命取り組めたかなと思う。
|
| |
|
| 6 |
成果と今後の課題 |
| |
(1) |
成果 |
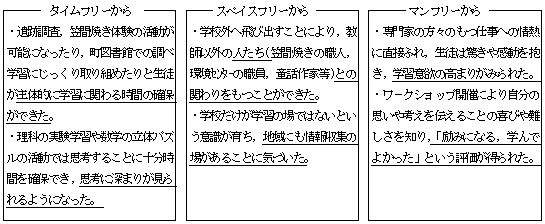 |
| |
(2) |
今後の課題 |
| |
|
ア |
常に魅力ある学習内容を開発し選択履修方法の研究を深め,多様化する生徒のニ-ズに対応していくこと。 |
| |
|
イ |
生徒のニ-ズにあった地域人材の発掘と活用に努め,累積していくこと。 |
| |
|
ウ |
生徒が自分の考えを相手に伝える方法を身に付けられるように,必修教科の指導の在り方を研究すること。 |
| |
|
エ |
必修教科を, 自ら課題を発見し解決していく力を育成する場として再編成すること。 |
| |
|
オ |
情報収集のしかたやワ-クショップによる自己表現の方法等を「総合的な学習の時間」にどう生かしていくかということ。 |