「総合的な学習の時間」の導入と教育課程の編成の工夫
―学校周辺の都市化が進むK小学校の事例― |
| 1 |
研究のねらい |
| |
本校では「総合的な学習の時間」の研究は2年次となる。本年度は,児童の総合的に学ぶ力をより高め,特に児童の問題解決の能力を発達段階に応じて育成することをねらいとした。そのために,総合的な学習を教育課程の中に具体的・効果的に位置付けるための方策について研究し,年間計画と週時程の編成の工夫,児童の活動を保障するための支援の在り方に主眼を置いた研究を進めることとした。 |
| |
|
| 2 |
基本的な考え方 |
| |
(1) |
「総合的な学習の時間」を日常の教育活動の一つとして円滑に導入する。 |
| |
(2) |
児童に身につけさせたい力を明確にし,評価と改善を常に行う。 |
| |
(3) |
児童主体の活動となるよう興味関心に基づいたテーマ設定をし,効果的に学ぶ力や問題解決能力をつけるとともに,基礎的・基本的な内容の定着を図る教育課程を編成する。 |
| |
|
| 3 |
学校と地域の実態 |
| |
新県庁舎に隣接し都市化の進む学区である。児童数は409人,12学級の中規模校である。学区は県庁舎周辺施設をはじめ,様々な公共施設や民間施設の移転が進み,社会的な変化が大きい。一方,田畑や林は残っているが,自然観察などができる豊かな環境があるとは言えない。昼間人口が多い都市型の人口構成であり,人口の流出入はあまりなく児童数は減少傾向にある。児童は素直で明るく,あいさつなどもよくできるが,生活体験が少ない。最近,地域内で交流を大切にする気運が高まり,地域のお祭りなども行われ,ゲスト・ティーチャーとして学校に協力するなど,地域や保護者は学校に積極的にかかわる機運が生まれている。 |
| |
|
| 4 |
総合的な学習を導入するための具体的方策 |
| |
(1) |
「総合的な学習の時間」の設置の手順 |
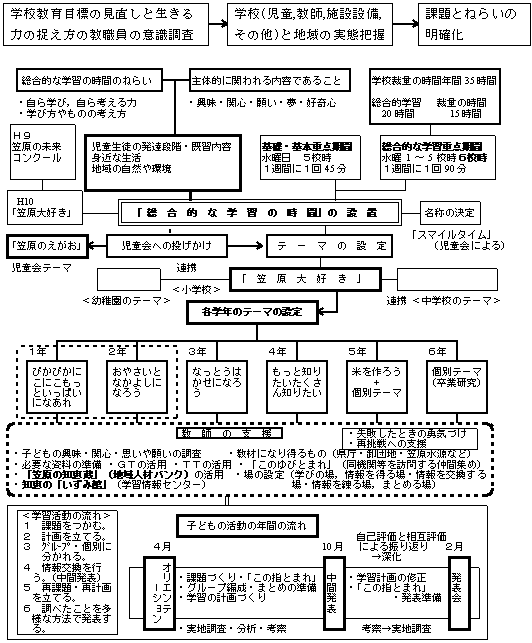 |
| |
(2) |
「総合的な学習の時間」の導入のための教育課程の編成の工夫 |
| |
|
ア |
授業時数及び週時程の工夫 |
| |
|
|
(ア) |
時数の確保:学校裁量の時間の活用(年間35時間を原則) |
| |
|
|
(イ) |
週時程の工夫:水曜日5校時を「総合的な学習の時間」として設定,総合的な学 習重点期間は午前中短縮5時間,午後の90分を1単位時間としてまとめ取りを行う。 |
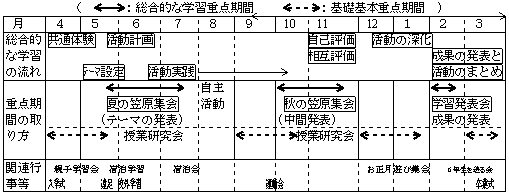 |
| |
|
イ |
年間計画:児童の問題解決の過程と重点期間の考え方,学校行事との組み合わせ |
| |
(3) |
問題解決のプロセスの構築とポートフォリオ法による記録の累積と評価の研究 |
| |
|
| 5 |
評価の工夫 |
| |
育課程・活動計画・支援の方法については,定期的な職員研修で,評価と改善を一体に
した研究を行った。児童の活動の評価を,スマイルカードによる相互評価と自己評価,記録
の積み重ねを分析して,身についた力や役立てられた基礎・基本の内容を把握する。 |
| |
|
| 6 |
成果と今後の課題 |
| |
児童の共通体験や問題解決活動の時間が充実し,課題意識が目に見えて高まるなど問題解決能力が身についてきた。また思考過程を把握して,教師が適切な支援を行うことができた。
今後は地域との連携と活動内容の多様化,素材の開発を図っていきたい。 |