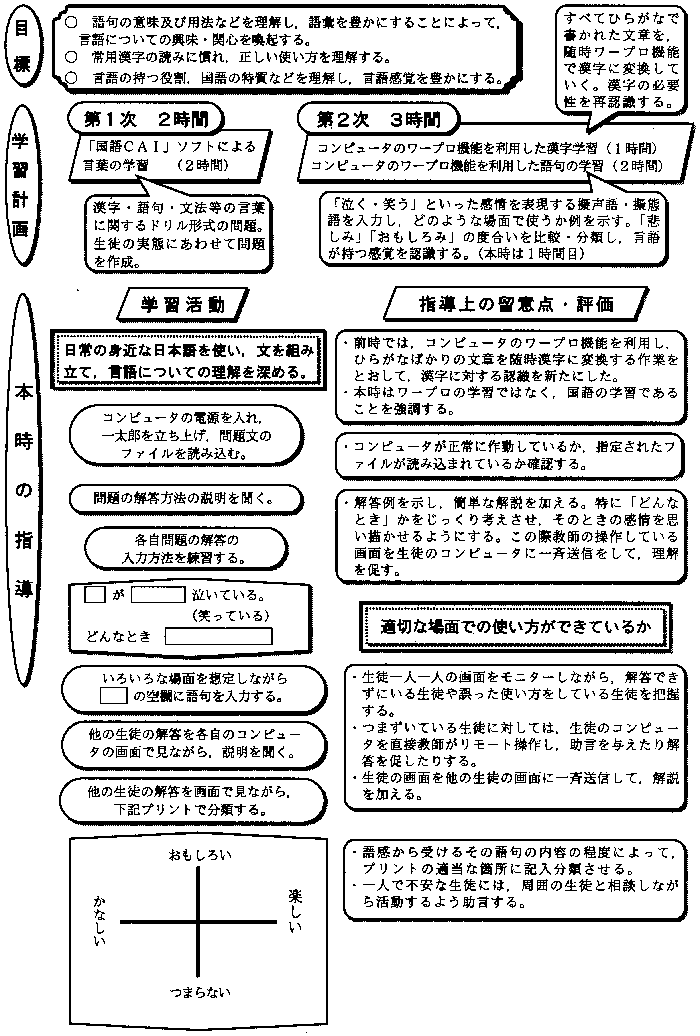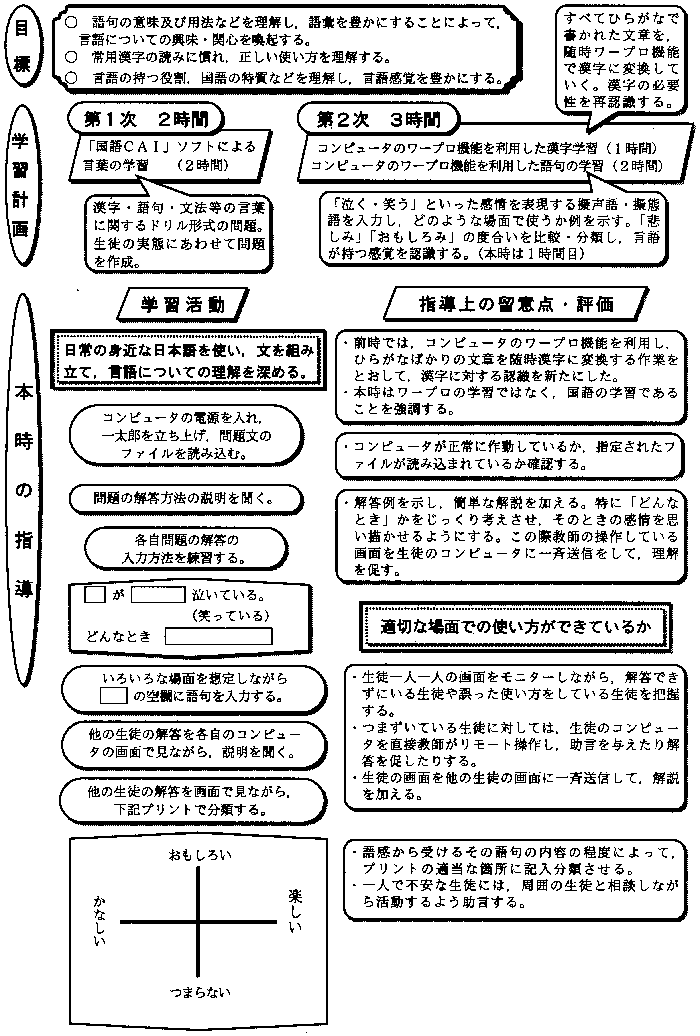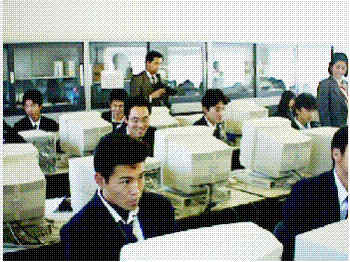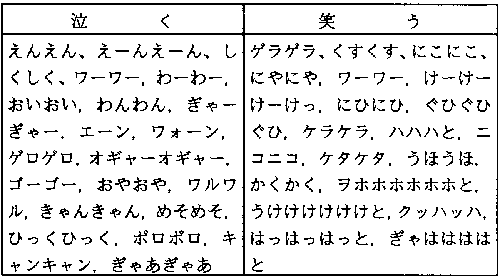| (1) |
興味・関心の喚起
| ア |
「国語CAI」ソフトによる漢字・語句の学習
問題部分を生徒の実態にあわせて作成したドリル型のソフトを使用した。 |
| イ |
コンピュータのワープロ機能を利用した漢字・語句の学習
| (ア) |
漢字の学習
すべてひらがなで書かれた文章がいかに読みづらいかを体験し,漢字に変換する作業を通じ,漢字の必要性を再認識することができるのでないかと思い,コンピュータのワープロ機能を利用することを考えた。 |
| (イ) |
語句の学習(本時)
人間の「泣く,笑う」という感情を表現する擬態語・擬声語等を,いくつか記入し,どのような場面で使うか例を示すことにより,その言語がもつ感覚を認識することができるであろうと考えた。さらに,経験・体験等に裏付けられた自分の言語感覚を基に,その言語がもつ「悲しみ,おもしろみ」をその度合いにより比較・分類することによって,改めてその言語から受ける感覚を整理するのに役立つであろうと考えた。 |
|
|
| (2) |
指導方法の工夫
| ア |
コンピュータのリモート操作による個別指導
一生徒のコンピュータをリモート操作で教師が直接コントロールすることができる。生徒の画面を随時モニターしながら,必要があれば,教師側から生徒のコンピュータの画面にヒントやメッセージを送ったり訂正したりすることにより,他の生徒に分からないように指導することができる。教師は教室内を移動せずに的確な助言をタイムリーな形で与えることができ,効果的な指導が可能になると考えた。 |
| イ |
コンピュータを生かした学習成果の交流
積極的に発表したいという生徒が少ないため,一生徒のコンピュータの画面を他の生徒全員に中継するという,間接的な発表形式をとることを考えた。生徒は誰の解答か分からないので,誤答であっても他の生徒の参考として全生徒の画面に提示できる。また,スライドのように次々と表示することができるので,言葉から受ける感覚が新鮮なうちに作業を進めることができると考えた。 |
|
| (3) |
イメージの視覚化
言葉から受けるイメージをそれぞれ比較し図示することで,改めてその言語から受ける感覚を整理することができると考えた。 |